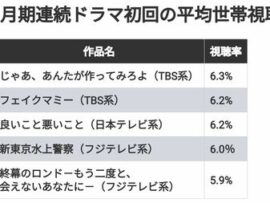米国務省は22日、国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)からの脱退を正式に発表しました。この決定は、ユネスコの活動が米国の国益に反し、イスラエルに対して不公平な対応をとっているとの見解に基づいています。トランプ大統領が1月の再就任直後から検討を指示しており、第1次トランプ政権以来となる今回の脱退は、2026年末に正式に発効する予定です。
 ユネスコ再脱退の決定を主導したトランプ前米大統領。国際機関との関係性再考を求める姿勢を示す。
ユネスコ再脱退の決定を主導したトランプ前米大統領。国際機関との関係性再考を求める姿勢を示す。
再脱退の背景と米国の主張
米国務省のタミー・ブルース報道官は22日の声明で、ユネスコがパレスチナを加盟国として承認している現状を「極めて問題があり、米国の政策に反する」と強く指摘しました。さらに、これが「組織内で反イスラエル的な見解の蔓延につながった」と批判し、今回の脱退理由の核心としました。トランプ大統領は再任後すぐにユネスコからの離脱検討を指示しており、同日中にオードレ・アズレ事務局長へ離脱決定を通告しました。
ユネスコとの歴史:離脱と復帰の繰り返し
米国は過去にもユネスコとの間で離脱と復帰を繰り返してきました。第1次トランプ政権下の2017年には、ユネスコがパレスチナ自治区の「ヘブロン旧市街」を世界遺産に登録したことに反発し、脱退を表明。2018年に正式に離脱しました。しかし、バイデン前政権下の2023年7月には、国際協調主義への回帰を掲げ、ユネスコへの復帰を果たしたばかりでした。今回の再脱退は、わずか3年足らずでの政策転換を意味します。
ユネスコ事務局長の声明と組織の対応
米国が再び脱退の意向を表明したことを受け、アズレ事務局長は22日、「深く遺憾に思う」との声明を発表しました。同事務局長は、今回の決定が「多国間主義の原則に反する」としてトランプ政権の判断を批判する一方で、「(脱退の)表明は予想されており、ユネスコは備えてきた」とも述べました。これにより、最大の拠出国である米国の分担金がなくなったとしても、組織としての財源確保は可能であると強調し、運営への影響を最小限に抑える準備があることを示唆しました。
ユネスコの概要と主要国の分担金
国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)は、1946年に発足した国連の専門機関です。その活動は、世界遺産の登録や保全といった文化・教育分野に留まらず、近年では人工知能(AI)に関する国際的規範の議論推進など、科学技術分野にも広がりを見せています。米国を含む194の国・地域が加盟しており、今年の分担金比率では米国が22%で最も高く、中国(20%)、そして日本(7%)がそれに続いています。日本の分担金が上位に位置していることは、ユネスコにおける日本の役割の重要性を示しています。
まとめ
今回の米国のユネスコ再脱退は、国際協調主義からの後退を示唆し、世界の多国間主義に大きな影響を与える可能性があります。特に、紛争地域における文化遺産保護や、AIなどの新興技術に関する国際的な枠組み形成といったユネスコの重要な役割に、今後どのような影響が及ぶか、国際社会の注目が集まっています。
参考文献
- Source link (Yahoo!ニュース, 共同通信/読売新聞からの転載記事)