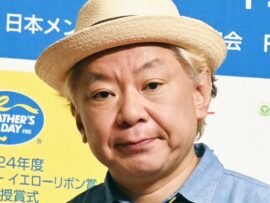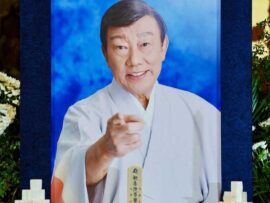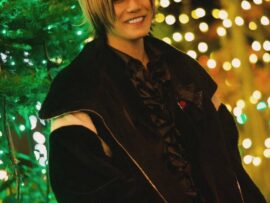職場における人間関係の悩みは尽きることがありません。特に「苦手な上司」との関係は、多くのビジネスパーソンにとって深刻なストレス源となり得ます。声を聞くだけで心臓が速くなったり、パフォーマンスが低下したりする経験は珍しくありません。脳神経外科医の菅原道仁氏は、このような状況は、脳の扁桃体(へんとうたい)が相手を「生存を脅かす存在」として過剰に認識してしまうことに起因すると指摘します。本記事では、この脳の反応を理解し、扁桃体を穏やかに保つための具体的な脳科学的アプローチをご紹介します。
 職場で人間関係のストレスを感じ、疲弊する人のイメージ。苦手な上司との付き合い方に悩む様子を表す。
職場で人間関係のストレスを感じ、疲弊する人のイメージ。苦手な上司との付き合い方に悩む様子を表す。
職場における「苦手な人」との関係が生むストレスの悪循環
39歳の中村さんは、新しい部長が着任してから1年、その声を聞くだけで動悸がすると打ち明けました。些細なミスを他のメンバーの前で指摘されたことをきっかけに、部長に対する苦手意識が募っていったのです。周囲からは「気にしなくて大丈夫」と言われる程度の出来事でしたが、中村さんにとっては非常に大きな心理的負担となっていました。
このように、ミスを指摘された上司に対して扁桃体が過剰に反応するのは、脳が相手を脅威と認識する自然な防衛反応です。しかし、この状態が慢性化すると、以下のような悪循環に陥りやすくなります。
- 上司の声を聞くだけで過度な緊張や手の震えが生じる。
- ミスを恐れるあまり、本来の能力を発揮できなくなる。
- 帰宅後も上司のことが頭から離れず、精神的な疲弊が続く。
- 不眠に陥り、翌日の仕事のパフォーマンスがさらに低下する。
この悪循環を断ち切り、扁桃体の興奮を鎮めることが、職場でのストレス軽減には不可欠です。
扁桃体の過剰反応を鎮める脳科学的アプローチ
では、こうした状況下で扁桃体の反応をどのようにコントロールすれば良いのでしょうか。菅原氏が提唱する「映画化テクニック」と「身体化テクニック」の組み合わせが特に効果的です。
-
映画化テクニック:客観視による距離の確保
帰宅後、上司との出来事が頭の中で繰り返し再生され始めたら、まず深い呼吸をしながら、その場面をまるで映画のワンシーンのように客観的に眺めてみましょう。自分がスクリーンに映し出された映像を見ているような感覚で、一歩引いた視点から出来事を観察します。これにより、感情的な距離が生まれ、扁桃体の興奮が徐々に落ち着いていきます。 -
身体化テクニック:身体感覚への意識集中
次に、自分の体の状態に意識を向けます。肩に力が入りすぎていないか、呼吸が浅くなっていないかを確認し、力を抜いたり、深くゆっくりと呼吸し直したりします。このシンプルな実践によって、身体的な緊張が和らぎ、それに伴って扁桃体の興奮も鎮静化に向かいます。
これら二つのテクニックは、脳の感情中枢である扁桃体と、理性や客観性を司る前頭前野とのバランスを取り戻す上で非常に有効です。
GABA活性化で扁桃体ストレスを根本から解消
さらに、脳を落ち着かせる神経伝達物質であるGABA(ギャバ)の働きを高めることも重要です。GABAは、特に扁桃体の過剰な活動を抑制する効果があります。このGABAの活性化を促す簡単な方法の一つが、「夜、ぬるめのお風呂にゆっくりつかる」ことです。
温かい湯に浸かることで身体がリラックスし、副交感神経が優位になります。これにより、脳内でのGABAの生成が促され、その日のうちに扁桃体の興奮を鎮静化させることができます。日常的にこの習慣を取り入れることで、翌日へのネガティブな影響を最小限に抑え、職場の人間関係によるストレスから解放される手助けとなるでしょう。
まとめ
職場での人間関係、特に苦手な上司との付き合いは大きなストレスとなり得ますが、脳の仕組みを理解し、適切な対処法を実践することでその影響をコントロールすることが可能です。扁桃体の過剰な反応を「映画化テクニック」と「身体化テクニック」で客観的に捉え、さらにGABAの活性化を促す入浴法を取り入れることで、心の平穏を取り戻し、より快適な職場生活を送ることができるでしょう。
参考文献
- 菅原道仁『あの人を、脳から消す技術』サンマーク出版