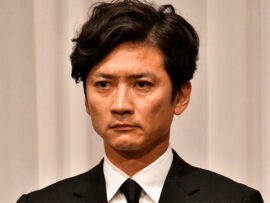科学は常に真実を追求するものとされていますが、その探求の過程において、あるいは意図せぬ形で「間違い」が生じることはないのでしょうか。ノーベル賞受賞者であるソール・パールマッター氏、ジョン・キャンベル氏、ロバート・マクーン氏は、科学にも間違いが存在し、その中には悪意なく生じるケースもあれば、妄信的な誤解や不正行為に起因するものもあると指摘しています。情報過多の現代において、私たちはどのように「良い科学」と「悪い科学」を見分け、誤った情報に惑わされないための思考を身につけるべきなのでしょうか。
「水の記憶」論文が投げかけた波紋
1988年、著名な科学誌『ネイチャー』に掲載されたあるフランスの研究チームの論文は、大きな議論を巻き起こしました。その内容は、特定の抗体を含む溶液を水で10の120乗回という天文学的な回数希釈した結果、ほとんど純水となった液体からも、元の溶液に見られた反応が一部確認されたというものでした。研究チームは、この現象を「元の溶液で起きた事象の記憶が、何らかの形で水の分子構造に保持されている」可能性として提唱しました。
 科学の論文や研究資料を調べる研究者や専門家の手元
科学の論文や研究資料を調べる研究者や専門家の手元
このような論文を、私たちはどのように捉えるべきでしょうか。このエピソードは、一般の私たちが科学的成果に関するニュースや記事に触れる際に直面する大きな問題を示しています。どれが画期的な新発見で、どれが誤った科学、あるいは偽科学の典型なのかを見分けることは非常に困難です。
この問題は、深刻な事態を招きかねません。例えば、愛する人が難病を患っている場合、「水の分子に記憶を保持する力がある」という説が、特定の病気の原因と同種の物質を天文学的に希釈して摂取すれば治癒すると主張する「ホメオパシー治療」に一縷の望みを抱かせるかもしれません。もし、このような記事が人々の判断を誤らせるものであれば、それは何百万もの人々に不必要な出費を強いるだけでなく、本当に効果のある治療機会を逸させ、健康を危険に晒すことにもつながりかねないのです。
「良い科学」と「悪い科学」を見分ける難しさ
「良い科学」と「悪い科学」を見分けるという問題は、本当に厄介です。なぜなら、そこには科学が期待に応えられない状況も、明らかにインチキなものに正当性を持たせるために科学の力を装っている状況もすべて含まれるからです。悪意なく正直に間違ったケースもあれば、妄想に取り憑かれて不正を働くケースもあります。
科学の理想は、適切に実践され、正しい結果を得ることです。私たちはまさにそうした「正しい科学的成果」を知りたいと願っているからこそ、科学関連の新聞記事や学術論文を読むわけです。
しかし、実際には「良い科学」からでも間違った結果が生まれることがあります。これは、科学が結果の「確信度」を表明するという性質を考えれば、むしろ当然のことと言えるでしょう。確信度は、その結果が正しい確率を示し、専門家は常にこの確信度を意識しています。例えば、ある研究結果の確信度が95パーセントだと表明されている場合、それは最高の仕事をしたとしても、20回に1回は間違える可能性があることを意味します。つまり、世の中には、適切に行われた「良い科学」でありながら、間違った結果を報告している論文が存在するということです。確信度95パーセントを掲げている論文の少なくとも20分の1が、これに該当する計算になります。
確信度95パーセントの意味
確信度95パーセントは、統計的有意性を示す一般的な基準ですが、これは「結果が偶然ではない確率が95%」という意味であり、「結果が絶対に正しい確率が95%」という意味ではありません。残りの5%の可能性は常に存在し、これが「良い科学」であっても誤った結論に至る可能性を示唆しているのです。
科学情報と向き合うための結論
科学は、私たちの世界を理解し、生活を向上させる上で不可欠な営みです。しかし、その成果を鵜呑みにするのではなく、批判的な視点を持って向き合うことが求められます。特に健康や社会問題に関わる科学情報に接する際には、情報の出どころ、根拠の確かさ、そしてその情報がどこまで確信を持って語られているのかを見極める「科学的思考力」が重要となります。
偽情報や誤った科学に惑わされないためには、常に複数の情報源を参照し、専門家の見解を比較検討し、そして何よりも「疑う」ことを忘れない姿勢が不可欠です。
参考文献
-
ソール・パールマッター、ジョン・キャンベル、ロバート・マクーン『THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義 1000年古びない思考が身につく』(日経BP)
本記事は上記書籍の一部を再編集したものです。