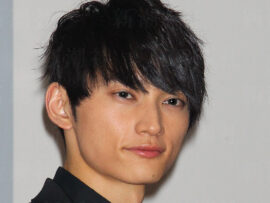先の参議院選挙で自公連立与党が過半数を割り込んだにもかかわらず、石破茂首相がその座に居座り続けている現状は、多くの国民に疑問を投げかけています。選挙で示された民意とは一体何だったのでしょうか。本稿では、憲政史研究家の倉山満氏による分析に基づき、各党の勝敗を分けた要因と、今後の日本政治がたどる道を詳細に解説します。
参院選結果と石破首相の「異例の」続投
石破茂首相の現在の行動は、一般的な政治の常識を超えています。通常、首相が掲げた目標議席を下回った場合、「開票終了を待たずに退陣表明」するのが通例ですが、今回は異例の事態が生じています。石破首相は続投会見で、「明日地震が起きるかもしれない」といった国民を呆れさせる言い訳や、「アメリカとの関税交渉がある」という建前を述べました。確かに、辞任が決まっている首相との交渉は意味をなしません。しかし、トランプ大統領は驚くべき速さで関税交渉を妥結させ、「石破首相、早く辞めてくれ」と言わんばかりの展開となりました。この動きは、石破首相が国際的な文脈でも孤立している可能性を示唆しています。
自民党が目指す「時間稼ぎ」戦略
大手紙では石破首相の退陣報道がされる一方で、首相自身はこれを打ち消しています。石破首相が続投に固執しているように見えますが、事態は首相個人の意思を超えています。自民党は今回の参議院だけでなく、そもそも衆議院でもすでに過半数を失っているのです。これにより、「自民党総裁=総理大臣」という戦後政治の定番の図式は崩壊しました。石破首相が辞めたくないと主張しても、理論上は強引に辞任させられる状況にあります。では、それでもなお最大勢力である自民党の真の意図は何でしょうか。倉山氏はこれをズバリ、「時間稼ぎ」と読んでいます。自民党は、状況がさらに悪化するのを避け、次の戦略を練るための猶予を求めているのかもしれません。
 第27回参議院選挙における自民党の特設サイトからの画像。石破首相が続投する中で、自公連立与党の過半数割れが日本の政治状況に与える影響を示す。
第27回参議院選挙における自民党の特設サイトからの画像。石破首相が続投する中で、自公連立与党の過半数割れが日本の政治状況に与える影響を示す。
参議院選挙の決定的な潮流と与党の敗北
現在の流れを理解するためには、今回の参議院選挙を改めて振り返る必要があります。多くの注目は参政党に集まりがちですが、それ以上に大きな潮流が存在しました。選挙前、自民党は114議席(非改選62)、公明党は27議席(非改選13)を保有しており、自公連立で50議席を獲得すれば過半数を維持できる、通常であれば「よほどのことがない限り負けない選挙」とされていました。しかし、まさにその「よほどのこと」が起きたのです。「火事は最初の5分間、選挙は最後の5分間」という言葉があるように、選挙は何が起こるか予測不能です。例えば、1989年の参議院選挙では、自民党が衆参同日選挙で大勝したわずか3年後に、土井たか子が歴史的な勝利を収め、「ねじれ国会」を招きました。
今回の選挙結果は、自民党が39議席を獲得し、公明党が8議席を獲得するという厳しいものでした。結果として、与党は全248議席中122議席にとどまり、過半数を割り込むこととなりました。これは単なる議席数の減少以上の意味を持ち、日本政治の新たな局面を象徴しています。
与党が過半数を割り込みながらも石破首相が続投するという前例のない状況は、日本政治の安定性に対する疑問を投げかけています。倉山満氏の分析が示すように、自民党の「時間稼ぎ」戦略は、次の政治的動きに大きな影響を与えるでしょう。国民の民意がどのように反映され、この政治的空白がどのように埋められていくのか、今後の日本政治の動向が注目されます。
Source: https://news.yahoo.co.jp/articles/267ea3e1ddf569501637e3faeff446e7cb744e3a