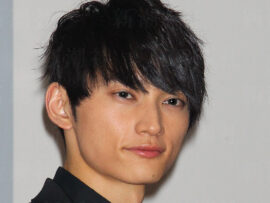ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が2000年の就任以来、国の実権を握り続けていることは周知の事実です。しかし、その人物像や行動原理の根底には何があるのでしょうか。軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏と東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠氏が、プーチン氏の深い内面と、彼を突き動かす「強いロシア」への執着、その形成過程を対談形式で分析します。
 クレムリンでの演説に臨むウラジーミル・プーチン大統領
クレムリンでの演説に臨むウラジーミル・プーチン大統領
「劣等民族」への転落から「強いロシア」へ:プーチンの原動力
黒井文太郎氏は、プーチン氏がエリツィン政権下でロシアが経験した「屈辱感」こそが、彼の原動力であると指摘します。プーチン氏は大統領就任当初からロシア民族主義、愛国主義を強く語ってきました。その根底には、共産主義ではない「超大国ソ連」への強い懐古主義があり、これはアメリカの「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン」に通じる「メイク・ロシア・グレート・アゲイン」という思想が根底にあると黒井氏は分析します。
ソ連崩壊後、ゴルバチョフ時代からエリツィン時代にかけてモスクワに居住していた黒井氏の体験からは、当時のロシア国民が手にした自由と同時に、世界から「破綻国家」と見なされ、国際社会で「劣等な民族」として扱われるという深い屈辱感を味わっていたことが浮き彫りになります。30代、40代をこの激動の時代に過ごしたプーチン氏と旧KGB出身のシロビキ(治安・国防機関出身者)たちは、この屈辱を晴らし、「世直し」として国を立て直していると強く信じているのです。しかし、その手法は旧KGB仕込みの謀略に満ち、邪魔者は排除するという問題も抱えていると黒井氏は言います。
エリツィン後継者としてのプーチン:初期の「御しやすさ」と変遷
小泉悠氏は、プーチン氏が最初から強大な権力を持っていたわけではないと分析します。エリツィン大統領によって後継者に抜擢された当初、モスクワの政界における影響力は限定的でした。むしろ、エリツィンの側近からは「エリツィンには忠実な人物であり、御し易い」人物と見なされていたのです。しかし、その後の彼の行動と権力の掌握は、初期の評価を大きく覆すものとなり、現在の地位を築き上げました。
結論
プーチン大統領の「強いロシア」への執念は、ソ連崩壊後の屈辱的な経験に深く根ざしており、旧KGB仕込みの行動原理と結びついています。この複雑な人物像を理解することは、今日の国際情勢、特に日本を取り巻く世界情勢を読み解き、将来の展開を予測する上で不可欠な視点と言えるでしょう。
参考資料
- 出典:『国際情勢を読み解く技術』(宝島社)より、軍事ジャーナリスト・黒井文太郎氏と東京大学先端科学技術研究センター准教授・小泉悠氏の対談
- 元記事:Yahoo!ニュース