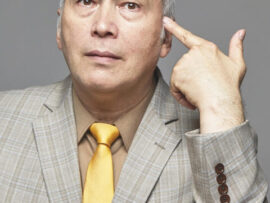バブル経済崩壊後の厳しい就職戦線を経験し、社会で不遇を強いられてきた「ロストジェネレーション(ロスジェネ)」世代。バブル崩壊から30年以上が経過したいまもなお、彼らは経済的・社会的な苦境に直面しています。この長年にわたる困難に対し、反貧困ネットワーク世話人で作家の雨宮処凛氏は、直近の参議院選挙が彼らにとって「最後の希望」であったものの、その期待が打ち砕かれたと語ります。本稿では、雨宮氏の視点から、今回の参院選がロスジェネ世代にどのような影響を与え、日本の社会が抱える格差問題にどう向き合うべきかを探ります。
参院選の主要争点、なぜ「ロスジェネ対策」は影を潜めたのか
今回の参議院選挙において、雨宮処凛氏が最も残念に感じたのは、本来重要な争点となるはずだった「ロスジェネ対策」が影を潜め、「外国人問題」が主要な論点として浮上してしまった点です。参院選の開始前には、政治の世界でもロスジェネ世代への支援策が注目され始めていました。自民党が今年に入ってから積極的にロスジェネ問題を取り上げる姿勢を見せたことで、長らく放置されてきたこの世代にようやく光が当てられるのではないかと、多くの関係者が期待を寄せていたのです。選挙直前まで掲げられていた具体的な対策への期待は、ロスジェネ世代の支援が前進する可能性を示唆していました。
しかし、選挙戦が進むにつれて状況は一変。「日本人ファースト」といった主張が前面に出て、各政党が外国人問題に焦点を当てる動きが顕著になりました。自民党は「違法外国人ゼロ」、国民民主党は「外国人への優遇見直し」などを掲げ、まるで外国人問題が日本全体にとって最も喫緊の課題であるかのように扱われたのです。結果として、物価高や減税といった経済問題を除けば、ロスジェネ世代の雇用や生活支援といった他の重要な争点は埋もれてしまいました。雨宮氏は、これは日本社会にとって計り知れない損失であり、真に必要な議論の機会が失われたことに大きな失望を表明しています。
50代に突入する「ロスジェネ世代」に残された時間と切実な願い
雨宮氏は、今回の参議院選挙が「最後のチャンス」だったという強い危機感を抱いています。ロスジェネ世代とは、主に1970年代から1984年頃に生まれた人々を指し、その多くはすでに50代に差し掛かっています。この年齢層に達したロスジェネ世代にとって、社会的な支援や環境整備は、文字通り時間との闘いとなっているのです。
彼らが長年訴え続けてきた根本的な願いは、「正社員になりたい人は正社員になれる」「結婚したい人は結婚できる」「子どもがほしい人は子どもを持てる」社会の実現です。しかし、特に女性の場合、出産には年齢的な限界があり、すでに10年ほど前からロスジェネ世代の女性からは「もう子どもを持つことは諦めた」という声が多く聞かれるようになっています。これは、社会構造が彼らの人生設計に大きな制約を与え続けてきた結果に他なりません。
 就職氷河期を経験し、日本の社会問題に直面するロストジェネレーション世代の日本人男性
就職氷河期を経験し、日本の社会問題に直面するロストジェネレーション世代の日本人男性
たとえ50歳であっても、まだ働くことは可能ですし、正社員を目指す道も残されています。しかし、この数年のうちに具体的な対策が講じられなければ、正社員として安定した職を得る機会は、さらに狭まる一方でしょう。彼らの多くは非正規雇用に甘んじており、このままでは老後の生活破綻や貧困問題が深刻化するリスクが高まります。参院選での議論が真の社会課題から逸れたことは、日本の将来にとって大きな痛手であり、ロスジェネ世代が直面するタイムリミットを浮き彫りにしています。
放置され続けるロスジェネ問題への警鐘と未来への課題
今回の参院選は、ロストジェネレーション世代が抱える問題の解決がいかに喫緊であるかを再認識させる機会となりました。雨宮処凛氏が指摘するように、「外国人問題」が前面に出る中で、長年にわたり社会の底辺で苦しんできた就職氷河期世代への支援が後回しにされたことは、日本の格差社会の根深さを改めて浮き彫りにしています。彼らが抱く「正社員になりたい」「家族を持ちたい」といった切実な願いは、個人の努力だけで解決できる問題ではなく、社会全体で取り組むべき構造的な課題です。
50代に突入し、「最後のチャンス」が刻々と失われつつあるロスジェネ世代。彼らが安定した生活を築き、社会の一員として活躍できるような環境を整備することは、単に特定の世代を救うだけでなく、少子高齢化が進む日本の活力を維持するためにも不可欠です。政治は目先の争点に囚われることなく、未来を見据えた真の社会課題解決に向けて、具体的な政策を推進していく責任があります。ロスジェネ問題への継続的な関心と行動こそが、より公平で持続可能な社会を築くための鍵となるでしょう。
参考文献:
- Yahoo!ニュース(提供:みんかぶプレミアム特集「格差社会サバイバル」第10回)
https://news.yahoo.co.jp/articles/452c60da90c1b966151e5263ee6a59723bbf1c4f