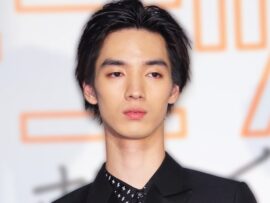先般行われた参院選と都議選において、石丸伸二氏が率いる地域政党「再生の道」は、いずれも獲得議席ゼロという厳しい結果に終わりました。かつて大きな注目を集め、「石丸旋風」とまで称されたその勢いは、本当に終焉を迎えてしまったのでしょうか。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は、著書『京大思考 石丸伸二はなぜ嫌われてしまうのか』を通じて、再生の道の掲げる「多選の制限」や「教育を最優先」といった政策は普遍的に納得できるものであると指摘。今回の選挙結果は、むしろ石丸氏の「まともさ」が裏目に出た可能性を示唆しています。本稿では、その失速の背景と専門家の見解を深掘りします。
かつての「石丸旋風」と都議選・参院選の厳しい現実
石丸伸二氏の政治団体「再生の道」の出発は、まさに華々しいものでした。都議選への立候補者募集には1128人もの応募が殺到し、3回にわたる試験とYouTubeで公開された最終面接の仕掛けは、多くの有権者の注目を集めました。しかし、最終的に選ばれた42人の候補者を35の選挙区に擁立したものの、結果は全員落選という厳しいものでした。
 地域政党「再生の道」代表の石丸伸二氏が街頭演説で支持を訴える様子
地域政党「再生の道」代表の石丸伸二氏が街頭演説で支持を訴える様子
都議選での総得票数は約41万票にとどまり、これは都知事選で石丸氏個人が得た票数のわずか4分の1に過ぎませんでした。知事選と議員選では有権者の選択基準が異なるため単純な比較はできませんが、昨年の熱狂を思えば、寂しい結果と言わざるを得ません。続く参院選では、東京選挙区から「再生の道」公認で出馬した吉田あや氏が約13万票を獲得しましたが、最下位当選の塩村文夏氏(立憲民主党)の約52万票には遠く及ばず、15番目の得票数でした。さらに、比例代表で立てた9人の候補者の合計得票数は東京都で11万票と、吉田氏個人の票数を下回り、都議選での総得票数の3分の1にも届きませんでした。
地上波露出の有無は本質的な問題か?
7月20日の投開票日に行われた記者会見で、石丸氏は「たとえば党首討論。地上波(テレビ)で呼んでいただきたかった。本当にそう思います」と述べていました。しかし、仮に党首討論に出演できたとして、それがどれほどの存在感を示すことに繋がったのか、疑問が残ります。
昨年の都知事選を振り返ると、石丸氏は小池百合子知事や蓮舫氏と比べて地上波での露出がはるかに少なかったにもかかわらず、次点に食い込むほどの勢いを見せました。その時の「旋風」を思えば、今回の結果を受けて「石丸旋風は終わった」と判断されても仕方ないでしょう。では、なぜ、この2回の選挙で石丸氏の勢いは止まってしまったのでしょうか。
専門家が指摘する「まともさ」が招いた結果
前述の鈴木洋仁准教授は、再生の道が掲げる「多選の制限」や「教育を最優先」といった主張は、誰が聞いても納得できる、ある意味「まとも」な政策であると評価しています。しかし、今回の選挙では、その「まともさ」が思わぬ形で仇となった可能性を指摘しています。
極めて常識的で、誰もが賛同しやすい政策は、逆に言えば、既存の政治への不満や強い変革を求める有権者の心に、決定的なインパクトを与えるには至らなかったのかもしれません。政治に疲弊し、強いメッセージや既存勢力との明確な対立軸を求める有権者にとって、「まともさ」は熱狂的な支持行動、すなわち投票行動へと繋がる強い動機付けにはなりにくいという現実が浮き彫りになったと言えるでしょう。
結論
石丸伸二氏と「再生の道」が、都議選・参院選で議席を獲得できなかった背景には、単なるメディア露出の不足だけではない、より深層的な要因が存在していると考えられます。鈴木洋仁准教授が指摘するように、その「まともさ」が、むしろ多様な価値観が交錯する現代政治において、求心力を欠く結果を招いた可能性があります。有権者の期待と政治家のメッセージの間に生じたこのギャップは、「石丸旋風」が一時的なものに終わった理由を解き明かす鍵となるかもしれません。
参考文献
石丸伸二はなぜ嫌われてしまうのか 都議選・参院選で「再生の道」は議席ゼロに終わった「石丸旋風」の「まともさ」が仇となったのか | PRESIDENT Online