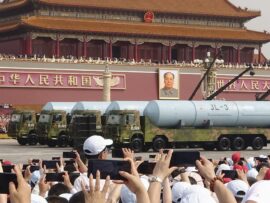火山学的に「いつ噴火してもおかしくない」と分析されている富士山は、ひとたび噴火すれば日本社会に甚大な被害をもたらすことが想定されています。京都大学名誉教授の鎌田浩毅氏も、高温の溶岩流や火砕流による多くの犠牲者だけでなく、広範囲に及ぶ火山灰の被害が「最も厄介」であると警鐘を鳴らしています。この火山灰は陸・海・空すべての交通機関を麻痺させ、ほぼ全産業に大打撃を与える恐れがあるというのです。本稿では、富士山噴火がもたらす溶岩流と火山灰の具体的な脅威について、詳細に解説します。
噴火が「いつ起きてもおかしくない」富士山の現状
富士山は現在、300年間にわたりマグマを溜め込んでいる状態にあり、火山学の専門家からは「いつ噴火してもおかしくない」という見解が示されています。実際に噴火が発生した場合、この膨大な量のマグマが一気に放出されることで、大規模な噴火となり、広範囲にわたる壊滅的な被害が予想されます。中でも特に懸念されるのが、高温の溶岩流と広範囲に飛散する火山灰による影響です。
800~1200℃の溶岩流が全てを焼き尽くす
富士山噴火の懸念現象の一つに「溶岩流」があります。これは、富士山内部のマグマが火口から噴出し、地形に沿って流れ下る現象です。近隣の森林、住宅、学校、道路といったあらゆるものを、800度から1200度という超高温の溶岩が飲み込み、全てを焼き払うでしょう。溶岩はその後、数カ月から1年という長い時間をかけて冷え固まり、その地は不毛の地と化します。
溶岩流が海や川、湖に到達した場合、水蒸気爆発を引き起こす可能性もあります。これにより、水に触れたマグマや岩石が粉砕され、周囲に火山灰や噴石をまき散らす恐れもあります。溶岩流が流れ込んだ地域は、町としての機能を完全に失うだけでなく、その場にいた生命さえも奪ってしまうのです。
富士山の溶岩流の特性:低粘度と膨大な量
溶岩流の挙動は、溶岩の「粘性」によって大きく異なります。粘性が低ければ水のようにサラサラと速く流れ、高ければドロドロとゆっくりと進みます。この粘性は、温度と「二酸化珪素(SiO2)」の含有量で決まり、低温で二酸化珪素が多いほど粘り気が強くなります。
しかし、富士山の溶岩は二酸化珪素の含有量が比較的少ない玄武岩質であるため、粘度が低く、非常にサラサラしています。この特性により、ひとたび噴火が起これば、溶岩流が広範囲にわたって流れ下ると予測されています。その速度は、人が走る速度とほぼ同じかそれ以上と言われていますが、冷えるにつれて粘度が高まり、下流では速度が落ちていきます。
 富士山噴火時の溶岩流のイメージ。高温の溶岩が地形を流れ下り、周囲の森や建物を破壊する様子
富士山噴火時の溶岩流のイメージ。高温の溶岩が地形を流れ下り、周囲の森や建物を破壊する様子
富士山の溶岩流は、その量の多さでも知られています。例えば、864年から866年にかけて発生した「貞観噴火」では、大量に流れ出た青木ヶ原溶岩流が、かつて富士山北麓にあった「剗海(せのうみ)」という湖を分断し、現在の西湖と精進湖を形成したと考えられています。これは、大規模な湖を地形から消し去るほどの威力を溶岩流が持っていたことを示しており、富士山が噴火すれば、膨大な量の溶岩が広範囲に及ぶことは確実です。
最も厄介な「火山灰」が社会機能に与える壊滅的打撃
溶岩流の脅威もさることながら、鎌田浩毅氏が「最も厄介」と指摘するのが火山灰です。火山灰は溶岩流のように特定の場所を焼き尽くすわけではありませんが、広範囲にわたり、社会のあらゆる機能を麻痺させる深刻な影響をもたらします。
火山灰は微細な粒子でありながら、重く、硬く、電気を帯びているため、以下のような壊滅的な被害が想定されます。
- 交通機関の麻痺: 空港の閉鎖による航空便の運休、鉄道レールの腐食やポイント故障、道路の視界不良と路面状況の悪化による車両通行不能など、陸海空すべての交通網が寸断されます。
- インフラへの影響: 送電線のショートや変電所の機能停止による大規模停電、浄水施設の損傷による断水、通信機器への浸入による通信障害など、ライフラインが停止する恐れがあります。
- 健康被害: 火山灰の吸入による呼吸器系の疾患、目や皮膚への刺激など、広範囲の住民に健康上の問題を引き起こします。
- 経済活動への打撃: 農作物への被害、工場の機械故障、観光業の壊滅など、ほぼ全ての産業活動に大打撃を与え、復旧には膨大な時間とコストがかかります。
特に、風向きによっては首都圏にまで火山灰が到達する可能性があり、その影響は日本経済全体を揺るがす規模になることが懸念されています。
結論:噴火の脅威への理解と備えが不可欠
富士山の噴火は、単なる自然現象に留まらず、私たちの社会、経済、そして生命に直接的な脅威をもたらします。高温の溶岩流による破壊、そして広範囲にわたる火山灰による社会機能の麻痺は、私たちの想像をはるかに超える規模の災害となるでしょう。
このような現実的なリスクを理解し、一人ひとりが適切な防災知識を身につけ、政府や自治体が連携して具体的な避難計画やインフラ対策を強化することが、来るべき大災害から私たち自身と社会を守るための急務と言えるでしょう。
参考文献
- 鎌田浩毅 著, 『災害列島の正体 地学で解き明かす日本列島の起源』, 扶桑社新書, 2025年.
- Yahoo!ニュース, 「富士山が噴火したらどうなるのか。京都大学名誉教授の鎌田浩毅さんは…」, PRESIDENT Online, 2025年9月3日. (https://news.yahoo.co.jp/articles/85497de96301b1a77691e9ebda0d15d89c52556e)