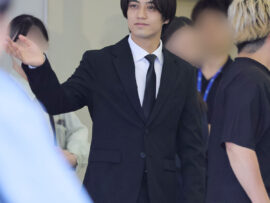10代にとって最大の関心事の一つである「大学受験」。現在の日本社会において、希望する進路に進む確率を高め、将来の選択肢を広げる上で、その重要性は計り知れません。この複雑な時代に、自分らしい進路を見つけるための指南書として、書籍『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売されました。本記事では、発刊を記念し、著者であるびーやま氏の特別インタビューから、多くの人が疑問に思う「学力」と「地頭」の関係について深掘りします。
「学力」と「地頭」は密接に連動する
世間では「学力と地頭は別物」という意見も聞かれますが、びーやま氏はその考えに異を唱え、両者は密接に連動していると語ります。詳しく掘り下げてみましょう。
びーやま氏によれば、たとえ高学歴でなくとも頭の回転が速いと感じる人は確かに存在します。しかし、そういった人々は、もし真剣に学んでいれば、より良い大学に進学できた可能性が高いと指摘します。実際に、学歴がない優れた経営者などと対話すると、その論理的思考力や問題解決能力の高さに驚かされると言います。
論理的思考力とひらめきを鍛える学問
一般的に「地頭が良い」とは、論理的な思考力や、困難な問題に対するひらめきの能力を指します。びーやま氏は、これらの能力は大学受験の学習過程で十分に養うことが可能だと強調します。
 高校生が数学の参考書を前に集中して学習している様子。問題解決能力や論理的思考力を高める受験勉強
高校生が数学の参考書を前に集中して学習している様子。問題解決能力や論理的思考力を高める受験勉強
例えば、数学の学習は、複雑な問題を解くために論理的な順序立てて考える力を養うだけでなく、時には既成概念にとらわれない新しい解法を発見する「ひらめき」も要求されます。このように、学力を高めるための勉強は、結果として地頭を鍛える有効な手段となるのです。したがって、びーやま氏の考えでは、学力と地頭は切っても切り離せない関係にあると言えます。
なぜ社会は「学力」で人を評価するのか
では、なぜ地頭の重要性が理解されつつも、社会では依然として学力による評価が主流なのでしょうか。びーやま氏はこの問いに対し、シンプルに「地頭を数値化する術がないから」と答えます。地頭の重要性は誰もが認めるところですが、それを客観的かつ簡便に評価する明確な方法が確立されていないのが現状です。そのため、ある程度、数値として現れる「学力」が、現状では最も分かりやすい評価基準となっているのは避けられない現実だと言えるでしょう。
さらに、びーやま氏は、本当に地頭が良い人であれば、このような社会の評価の仕組みや、地頭が数値化されにくい現実にも自然と気づくはずだと補足します。学力を通じた努力は、地頭を磨き、さらには社会の構造を理解する洞察力をも育むことに繋がるのかもしれません。
まとめ
びーやま氏の洞察は、「学力」と「地頭」が決して対立するものではなく、むしろ相補的な関係にあることを示唆しています。大学受験に向けた学習は、単なる知識の詰め込みに留まらず、論理的思考力やひらめきといった真の「地頭」を鍛え上げる貴重な機会となり得ます。自身のキャリアや人生の選択肢を広げるためにも、学力向上への努力は、未来を切り開くための賢明な投資と言えるでしょう。
参考資料
- びーやま氏著:『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』(ダイヤモンド社)
Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/31d4ebfeff272da304f10abee5882b2c6b0b0072