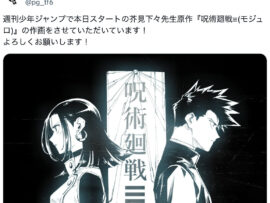近年、日本社会では生活保護利用者や外国人に対するバッシングが顕著に増加しています。特に、その背景には政治的な意図が隠されているのではないかという指摘も少なくありません。この現象はなぜこれほどまでに強まっているのでしょうか。生活困窮者支援に長年取り組み、『生活保護と外国人』(明石書店)の著者でもある、つくろい東京ファンド事務局長の大澤優真氏に、その実態と深層について詳細を伺いました。
日本における外国人・生活保護バッシングの現状と背景
大澤氏は、在留資格を持たない仮放免者などの外国人支援を通じて、外国人へのバッシングが以前から存在していたことを肌で感じてきたと語ります。しかし、2025年に入って国民民主党や参政党などがこの問題を公に採り上げるようになってから、その強度がこれまでにないレベルで増していると指摘します。
具体的な例として、群馬県桐生市で生活保護費が1日1000円ずつ手渡されるという異常な運用が発覚した際も、本来であれば「桐生市の運用が問題」と批判されるべきところが、なぜかその次に外国人が攻撃の対象となる現象が見られました。さらに、2025年6月に最高裁が生活保護基準の1割引き下げを違法と判断した際にも、判決内容とは直接関係のない外国人が非難されるという不可解な事態が発生しました。これらの事例は、特定の社会層への攻撃が、しばしば論点とは無関係に拡大される傾向にあることを示唆しています。
排外主義的なバッシングを煽る三つの要因
大澤氏は、なぜこのようなバッシングが生じるのかについて、主に三つの要因が複雑に絡み合っていると分析します。
一つ目は、外国人と身近に接する機会が少ない人々による事実誤認や誤った先入観です。情報源が限られる中で、偏った情報が先行し、それがステレオタイプな認識を形成してしまいます。
二つ目は、一部の政治家による意図的な扇動です。大澤氏は、これらの政治家が正確な事実を認識した上で、あえて事実に反する発言を行い、排外主義的な感情を煽っていると見ています。例えば、旧大蔵省や財務省の官僚出身の政治家が政府統計を見ずに発言しているとは考えにくく、その発言には明確な意図がある可能性が高いと指摘します。
三つ目は、事実にそもそも関心がない人々です。彼らはアクセス数や注目度を稼ぐことを最優先とし、批判されるとすぐに投稿を削除するような無責任な行動を取りがちです。このような層が、根拠のない言説を拡散させる一因となっています。
 参議院選挙の街頭演説に集まる有権者と市民の様子。政治家の発言に対する世論の動向を示す。
参議院選挙の街頭演説に集まる有権者と市民の様子。政治家の発言に対する世論の動向を示す。
政治家の「人気取り」戦略とその影響
このような行動が政治家にとって何の利益になるのか、との問いに対し、大澤氏は「結局、人気取りだろう」と断言します。外国人だけでなく、障害者や生活保護利用者といった少数者、いわゆる「弱い立場の人たち」を標的にすることで、「どうせ叩いても反撃してこないだろう」という思惑が働くというのです。
政治家が人気取りのためにバッシングを続けるのであれば、有権者自身が事実を正しく知り、そうした扇動に加担しない姿勢を示すことが重要であると大澤氏は強調します。事実に基づいた発言をする政治家がより評価される社会になれば、この問題は改善に向かう可能性があると希望を述べます。
また、「日本人ファースト」といったスローガンについては、その欺瞞性を指摘します。日本の外国人人口の割合はわずか3%であり、残りの97%は日本国籍保有者であるにもかかわらず、「日本人ファースト」と掲げること自体に意味を見出せないと述べます。政治家には、たとえ票につながると思っても「これは言ってはいけない」という倫理的な一線があるはずだとし、近年その一線が急速に崩壊していることに強い懸念を示しています。
結論:情報への意識と社会の成熟が求められる
外国人や生活保護利用者に対するバッシングの増加は、単なる社会の分断ではなく、一部の政治家による意図的な「人気取り」戦略と、事実への無関心が複合的に絡み合って生じている深刻な社会問題です。特に、弱者を標的とした攻撃は、民主主義社会の根幹を揺るがしかねない危険性をはらんでいます。
この問題に対処するためには、まず有権者一人ひとりが情報の真偽を見極める力を養い、安易な排外主義的な言説に流されないよう意識を高めることが不可欠です。そして、事実に基づき、社会の多様性を尊重する政治家を積極的に評価する動きが広がることで、健全な政治議論と社会の成熟が促されることが期待されます。
参考資料
- 大澤優真 (2020). 『生活保護と外国人』 明石書店.
- つくろい東京ファンド 公式ウェブサイト. (活動内容に関する情報).