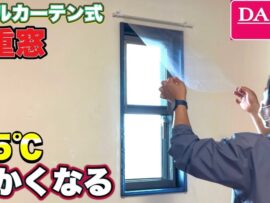近年、日本国内で米価の高騰が続いており、消費者や業界関係者の間で大きな関心事となっています。当初、国や農林水産省は「流通の目詰まり」が価格上昇の主因であると説明してきましたが、広範な調査の結果、その見解は覆されました。2025年8月5日、石破茂首相は米価高騰の主な原因が「生産量の不足」にあることを正式に認め、これまでの政府説明との食い違いが浮き彫りとなりました。
 米価高騰対策の閣僚会議に臨む石破茂首相と小泉進次郎農水相
米価高騰対策の閣僚会議に臨む石破茂首相と小泉進次郎農水相
「流通の悪者扱い」が招いた業界の憤り
農林水産省が主張してきた「流通の目詰まり」という概念は、流通業界に大きな波紋を広げました。特に、小泉進次郎農水相が流通を「ブラックボックス」とまで表現し、全ての米の出荷・販売業者に対し在庫量の報告を求める調査を発表した2025年6月17日以降、多くの米穀店や流通業者は不当な「悪者扱い」を受けたと感じていました。東京近郊で老舗米店を営む中村真一さん(仮名)は、「米をため込んで儲けているんでしょ、と客から言われることもあった。なぜ素直に謝れないのか」と、当時の憤りを露わに語っています。一時的にでも世論から疑いの目を向けられた流通側の心中は、察するに余りあります。
短期間の在庫調査が流通業者に与えた重圧
農水省が実施した在庫調査は、流通業者にとって実務上の大きな負担となりました。事業者は、2023年7月から2025年6月末までの仕入れ、在庫、精米、販売、それぞれの詳細な量を約2週間という短期間で報告するよう求められました。中村さんは、「米の収穫は年1回であり、米屋は年間販売量を予測して、次の収穫時期まで在庫を持つのが当然。そのコストもかかる」と述べ、小泉農水相の発言は業界の仕組みを全く無視した「思いつき」であったと批判しました。特に、高齢の店主が経営する小規模な米店にとっては、この報告作業は想像以上に大変なものとなり、「提出が任意であれば出さない」という怒りの声が同業者から多数寄せられたといいます。
農水省調査結果:流通目詰まりは確認されず
小泉農水相は2025年7月29日の記者会見で、米高騰の原因を検証するために実施した調査の終了を明らかにしました。その詳細な結果は翌30日、「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」という有識者会議で静かに示されました。速報値によると、今年6月末時点の米の在庫量は、農家、JAなどの集荷業者、小売り・中食・外食業者、いずれの段階でも前年並みであることが判明しました。この結果は、これまで農水省が主要因としてきた「流通の目詰まり」が実際には確認されなかったことを明確に示しています。「コメの流通、目詰まり確認されず 量が足りず値上がり? 農水省調査」と題された朝日新聞の記事をはじめ、各紙はこの調査結果を静かに報じました。
この調査結果と石破首相の認識により、米価高騰の真の原因は流通ではなく、供給量そのものの不足にあるという見方が強まりました。今後は、日本の食料安全保障における生産量の安定化と向上に向けた、より本質的な政策が求められることとなるでしょう。
参考文献
- 朝日新聞デジタル. 「コメの流通、目詰まり確認されず 量が足りず値上がり? 農水省調査」.
- AERA dot. 「【ガチで解説】コメ不足の真相を徹底解説【農水省の長年の説明は的外れだった】」. https://dot.asahi.com/articles/-/260297