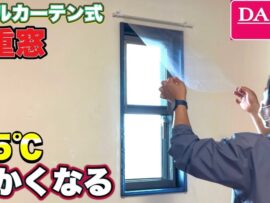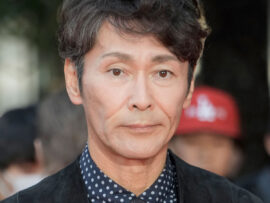SNSで頻繁に目にされる「子持ち様」という言葉は、公共の場での子連れへの配慮を求める声に対し、「特別扱いを要求している」という批判的な意味合いで使われがちです。しかし、子育て中の当事者が本当に求めているのは、こうした「優遇」なのでしょうか?こども家庭庁が実施した調査からは、意外な実態が明らかになりました。本記事では、こども家庭庁の安藤温子広報推進官への取材に基づき、「こどもまんなかアクション」の取り組みと、子育て当事者の本音について深掘りします。
「子持ち様」批判を乗り越える:こども家庭庁が推進する「こどもまんなかアクション」とは
「こどもまんなかアクション」とは、子どもや子育て中の方々が、様々な制度やサービスを気兼ねなく利用できる社会を目指し、地域社会、企業などあらゆる場で、年齢や性別に関わらず全ての人が子どもや子育て中の人々を応援する、社会全体の意識改革を後押しする取り組みです。こども家庭庁が発足直後の2023年6月から7月にかけて、子育て当事者を対象に「公共の場で困ったことや、どのようなサポートを求めているか」に関する調査を実施しました。
 「こどもまんなかアクション」を紹介するこども家庭庁のウェブサイト
「こどもまんなかアクション」を紹介するこども家庭庁のウェブサイト
この調査で浮かび上がってきたのは、多くの人が抱くイメージとは異なる実態でした。子育て当事者が求めていたのは、特定の「優遇」ではなく、むしろ「理解とちょっとした配慮」だったのです。
優遇ではなく「理解と配慮」を:子育て当事者の真のニーズ
調査結果は、「特別な支援をしてほしいのではなく、理解やちょっとした配慮がほしい」という子育て世帯の率直な声を浮き彫りにしました。具体的には、「席を譲ってほしい」「順番を優先してほしい」といった優遇を求める声よりも、「ベビーカーで困っているときに声をかけてもらえる」「子どもが泣いてしまっても『大丈夫だよ』と言ってもらえる」といった「気遣いや理解」に対するニーズが圧倒的に多数を占めていました。
こどもまんなかアクションの賛同を示す「こどもまんなかマーク」
これらのニーズは公共交通機関に限らず、職場や日常のささいな場面にも広がっており、社会全体での温かい「まなざし」が求められていることが明らかになりました。
社会全体の「まなざし」を変えるために:アクションの目指す未来
こうした現状を踏まえ、こども家庭庁は社会全体の意識改革、すなわち「気運醸成」と「意識改革」を目的としています。安藤広報推進官は、「もっとシンプルに言えば、子ども・若者や子育てをしている人を応援する人を増やしたい」と語ります。この強い思いが、「こどもまんなかアクション」の原動力となっています。社会全体で子育てを支える意識が高まることで、子育て世代がより安心して暮らせる未来を目指しているのです。
「こどもまんなかアクション」は、子育て中の人々が直面する課題に対し、単なる制度的な支援だけでなく、社会全体の意識変革を通じて、より温かく包容力のある環境を築こうとする重要な取り組みです。子育て支援は、特定の誰かを優遇することではなく、社会全体で未来を担う子どもたちとその親たちを支える、ごく自然な「理解と配慮」から始まるべきであると、改めて私たちに訴えかけています。