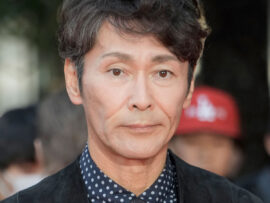世界各国でスポーツベッティングの合法化が加速する中、日本においてはその議論すらほとんど進んでいないのが現状です。大阪経済大学の相原正道教授は、この背景には日本の独特な法制度があり、スポーツベッティングという概念自体が想定されていないと指摘しています。国民の利益を考慮し、この現状を維持すべきか否かについて、早急な議論が求められています。
世界のスポーツベッティング合法化の現状と日本の特異性
2010年代以降、世界の主要国ではスポーツベッティングの合法化が加速度的に進んでいます。特に米国では、2018年に連邦最高裁がスポーツ賭博を禁じる「プロ・アマチュアスポーツ保護法(PASPA)」を違憲と判断して以来、各州が独自に合法化へと舵を切りました。2025年2月現在、全50州中38州に加え、ワシントンD.C.とプエルトリコも合法化を達成しています。米ゲーミング協会によると、2023年には米国人がスポーツに賭けた資金が前年比3割増の1198億ドル(約18兆円)に達し、業界収益も前年比4割増の109億ドルと過去最高を記録しました。
ヨーロッパでは、英国、フランス、ドイツ、イタリアといった主要国が国による認可とライセンス制度、厳格なガバナンスの下でスポーツベッティングを合法的に運営しています。さらに、オーストラリア、カナダ、南アフリカ、そしてアジア圏のフィリピンやシンガポールでも、制度整備が進められています。このような世界の潮流の中、先進国で唯一、スポーツベッティングを全面的に非合法とし続けているのが日本です。
日本における賭博罪と公営ギャンブルの法制度
日本でスポーツベッティングが合法化されない最大の要因は、刑法に規定される「賭博罪」の存在にあります。刑法第185条(賭博罪)および第186条(常習賭博罪)では、営利・非営利を問わず、原則として全ての賭博行為が禁止されています。この法体系は、戦後間もない1948年に制定されたもので、根本的な見直しはなされていません。つまり、日本の法制度そのものが、現代におけるスポーツベッティングという概念を想定していないのです。
 スポーツベッティングの概念を表すイメージ写真
スポーツベッティングの概念を表すイメージ写真
例外として、競馬、競輪、競艇、オートレースといった「公営ギャンブル」は、「特別法」によって明確に認められています。例えば、競馬は「競馬法」、競艇は「モーターボート競走法」に根拠が定められ、その収益は地方自治体や公益法人に還元される仕組みです。また、サッカーくじ「toto」も「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」に基づき、文部科学省所管の日本スポーツ振興センターが運営しており、公益性と収益の公共還元が合法化の前提条件となっています。
スポーツベッティング合法化への課題と過去の議論
スポーツベッティングの多くは民間運営を前提としているため、既存の公営ギャンブルの枠組みに乗せることが難しいという制度的な課題が存在します。しかし、これまでの公営ギャンブルに準じた形で、新たな仕組みを制度内に取り込むことは十分に可能であるとの見方もあります。日本の法制度がスポーツベッティングの概念を想定していないことが、日本が世界の市場から隔絶されている大きな要因と言えるでしょう。
過去にも、スポーツベッティングの合法化を巡る議論は何度か持ち上がりました。2000年代初頭のサッカーくじ「toto」導入時には、Jリーグの試合を対象とした賭け行為の是非が国会で議論されましたが、「教育的配慮」や「青少年への悪影響」といった道徳的理由から、最終的にくじ形式に限定されることとなりました。
公営ギャンブルとの兼ね合いと財源の問題
さらに注目すべきは、既存の公営ギャンブルとの兼ね合いです。競馬や競艇などは、地方自治体や一部官庁にとって貴重な財源となっています。もしスポーツベッティングが新たに導入されれば、この限られたパイを巡る奪い合いが生じる可能性があり、既存の既得権益との調整が大きな課題となります。
結論
世界中でスポーツベッティングの合法化が進み、その市場が急速に拡大する中で、日本がこの潮流から取り残されている現状は、法制度の根本的な見直しを促すものと言えます。賭博罪の存在、公営ギャンブルとの兼ね合い、そして民間運営の課題など、多岐にわたる障壁が存在しますが、現状維持が本当に国民の利益に資するのか、国際的な視点も踏まえた上で、より踏み込んだ議論が求められています。
参考文献:
- 相原正道『スポーツと賭博』(新潮新書)
- 日経ヴェリタス「スポーツ賭博、米国で急拡大 Z世代・市場熱狂の光と影」(2024年4月7日)
- スポーツ庁HP「スポーツ振興くじ」