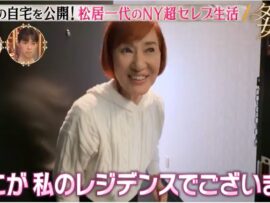「大相続時代」と呼ばれる現代において、10人に1人が相続税の課税対象となると言われています。「うちには財産がないから関係ない」と油断していると、思わぬ多額の相続税が発生するケースがあります。日本の相続税は遺産が1億円を超えると40%、6億円を超えると最高税率55%と世界でも高水準。富裕層が節税に励む一方、税務署の目は一般家庭にも向けられています。
 相続税の基礎控除引き下げと税務調査の強化を示すイメージイラスト
相続税の基礎控除引き下げと税務調査の強化を示すイメージイラスト
「まさか」の相続税:思わぬ落とし穴とは
都内に住む会社員の田中聡子さん(仮名・40代)の事例は、多くの人が陥りやすい罠を示しています。不動産会社を経営していた父親が多額の借金を残して他界。田中さんは借金を返済し、残った財産は基礎控除(母親と田中さんの2人で4200万円)を下回る4170万円だったため、相続税の申告を行いませんでした。しかし、父親の死から2年以上後、税務署から突然の連絡が。父親が兄弟を受取人にしていた生命保険が相続財産と見なされ、結果的に課税ラインを超過。田中さんと母親は計55万円を納税することになりました。納税額が低くても税務調査は行われるのです。
国税庁の狙い:なぜ「無申告」を徹底調査するのか
国税庁が「無申告」の調査に力を入れている背景には、2015年からの相続税法改正があります。基礎控除額が大幅に圧縮され、課税対象者はそれまでの5万人から一気に10万人以上へと倍増しました。これに伴い、課税ラインを超えても申告しない相続人が増加したとみられています。国税庁は、無申告を「自発的に適正な申告・納税を行っている納税者の公平感を著しく損なう」行為と位置付け、積極的に調査を進めています。これは、納税の公平性を保つための重要な取り組みです。
富裕層も油断禁物:生前贈与の盲点
もちろん、富裕層に対する税務調査はより厳しく行われます。中部地方のある建設会社社長は、非課税となる年間110万円の範囲内で、子供と孫の計5人に20年間生前贈与を続け、総額1億1000万円を移転。これにより2000万円の相続税を節税したつもりでした。しかし、社長の死後、遺族が相続税の申告を終えると、程なくして税務調査が入りました。これは、一連の贈与が「定期贈与」と見なされ、当初からまとまった財産を贈与する意図があったと判断された可能性が高く、結果として贈与税や相続税の追徴課税につながる典型的なケースです。
迫る大相続時代を乗り切るために
「大相続時代」において、相続税はもはや富裕層だけのものではありません。資産が少ないと感じる家庭でも、生命保険や過去の贈与など、思いがけない形で課税対象となることがあります。税務署はあらゆる層の相続に目を光らせており、安易な自己判断はリスクを伴います。相続税の発生に備え、事前に専門家と相談し、適切な対策を立てることが、将来の家族の負担を減らすための鍵となります。
出典:週刊東洋経済 (Original article)