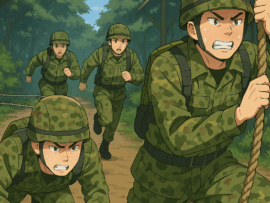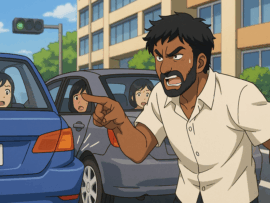世界を揺るがせた「トランプ・ショック」は、単なる短期的な「取引」として捉えられがちです。しかし、その本質は、現代の世界経済の構造と潮流が生み出した、より深く戦略的な動きにあります。特に日本では、関税率が合意に至ったことで一安心との見方もありますが、その背後にある歴史的、経済的意味を理解しなければ、今後の展開を正確に予測することはできません。本稿では、異能の評論家が著書『基軸通貨ドルの落日』で示した分析に基づき、「トランプ・ショック」が持つ意味と、世界経済の現在そして未来に関する考察を紹介します。
 基軸通貨ドルの落日』の書影。トランプ・ショックの背景と世界経済の未来を分析した書籍。
基軸通貨ドルの落日』の書影。トランプ・ショックの背景と世界経済の未来を分析した書籍。
「関税措置」は国際経済システム再編のための戦略的手段
トランプ政権が関税措置を打ち出したのは、国際経済システムをアメリカに有利な形へと再編するための手段として利用しようとしたためです。もちろん、関税という強力な武器を用いて世界全体を動かすことは、どの国にでもできることではありません。アメリカが持つ巨大な国内市場と、他国、特に輸出主導型経済体制の国々がその市場に深く依存しているからこそ、アメリカは関税という手段で他国を交渉のテーブルに着かせ、自国の利益を追求できるのです。
国際政治経済学における「リベラリズム」の考え方によれば、各国の経済的相互依存は当事国双方に利益をもたらし、その関係からの離脱は損害を伴います。例えば、戦争が貿易などの経済的相互依存を破壊するため、経済的には割に合わない行為となる、とされます。このため、世界各国の相互依存が深まれば、各国は対立や紛争を回避し、リベラルな国際秩序が実現すると考えられてきました。このリベラリズムは、冷戦終結後、アメリカをはじめとする先進諸国の外交戦略の中心的なイデオロギーとなり、アメリカがグローバリゼーションを推進し、中国のWTO加盟を支援したのも、このリベラリズムに基づく戦略の一環でした。
米中貿易戦争における中国の脆弱性
リベラリズムの観点からは、中国の製造業企業がアメリカへの輸出によって利益を得る一方で、アメリカの消費者は中国からの安価な製品を享受するという恩恵があります。したがって、アメリカが中国に関税を課すことは、中国の生産者だけでなく、アメリカの消費者にも損害を与える非合理的な行為であると考えられます。
しかし、トランプ政権は、中国の輸出企業がアメリカ市場に深く依存しているという状況を逆手に取り、関税を「脅し」として中国の政策変更を促そうとしています。このような戦略は、米中間の経済的相互依存が深化していた「にもかかわらず」ではなく、むしろ「深化していたからこそ」選択肢となり得たのです。
もちろん、対中関税はアメリカの消費者にも損害を与えるでしょうし、中国は報復としてアメリカからの輸入品に高関税を課す可能性が高いです。しかし、この関税の報復合戦となった場合、より大きな苦境に立たされるのは、貿易赤字国であるアメリカよりも、貿易黒字国である中国の方であると分析されています。中国経済は輸出、特にアメリカ市場への依存度が高く、これが関税によるダメージを拡大させる要因となるでしょう。
「トランプ・ショック」は、単なる一時的な経済摩擦ではなく、グローバル経済の根幹を揺るがし、国際秩序の再編を目指すアメリカの戦略的な動きです。この動きが世界経済、そして日本にどのような長期的な影響をもたらすか、引き続き注視していく必要があります。
参考文献
- 『基軸通貨ドルの落日』 著者不明 (記事中に言及あり)