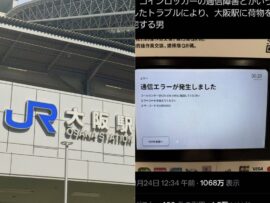近年、日本の豪雨は熱帯地域に匹敵する激しさを増し、全国各地で観測史上最多の雨量を記録しています。海面水温の上昇が水蒸気量を増加させ、広範囲かつ長期間にわたる豪雨を引き起こしているのが現状です。特に日本近海は、世界の平均を大きく上回る速度で温暖化が進行しており、豪雨はもはや「まさか」の出来事ではなく、「いつでもどこでも」起こり得る日常的な災害となりつつあります。三重大学大学院生物資源学研究科の立花義裕教授の著書『異常気象の未来予測』からの知見を基に、この新たな豪雨の様相とその背景にある課題を解説します。
 2024年能登半島豪雨の被害状況を示す航空写真。住宅地が広範囲に浸水し、地球温暖化による異常気象の影響を強く示唆している。
2024年能登半島豪雨の被害状況を示す航空写真。住宅地が広範囲に浸水し、地球温暖化による異常気象の影響を強く示唆している。
豪雨の激甚化と日本全国への拡大
地球温暖化が豪雨の増加に繋がっているという認識は広まりつつありますが、その具体的なメカニズムを理解している人はまだ少数です。かつての豪雨は九州や四国など一部の地域に限定されることがほとんどでしたが、現在では長野県、岩手県、北海道、瀬戸内海地域など、以前は雨が少なかった地域でも頻繁に発生しています。例えば、2024年には能登半島、秋田県、山形県など、全国の広範囲で豪雨災害が発生しました。
これにより、日本のどこにいても豪雨に遭遇する可能性がある時代となり、特に豪雨に慣れていない地域の人々にとっては、わずかな雨量でも甚大な被害に繋がりやすくなっています。これは日本に限った話ではなく、2024年のスペイン豪雨のように、元々雨量が少ない地域で未曾有の豪雨が発生し、災害が増幅するケースが世界中で見られます。総雨量と災害規模が必ずしも比例しないという認識が重要です。
線状降水帯を伴わない豪雨の特性と災害被害の背景
近年、豪雨のもう一つの特徴として、広範囲でより長期間降り続く「広域長期型」が増加している点が挙げられます。従来の狭い範囲に短時間で大量に降る集中豪雨とは異なり、被害地域も広範囲に及びます。線状降水帯は狭い範囲に豪雨をもたらす現象として知られていますが、最近の豪雨には、必ずしも線状降水帯を主因としない例が増えています。
その象徴的な例が、2018年の西日本豪雨です。この豪雨は線状降水帯が主な原因ではなかったにもかかわらず、長野県以西の広範囲と北海道で、72時間降水量が観測史上最大を記録しました。気象庁は3日前に緊急記者会見を開き、ほぼ完璧な精度で予測を行い、浸水域もハザードマップとほぼ一致していました。しかし、これほどの予測精度とマスメディア、さらにはネットメディアによる徹底的な注意喚起があったにもかかわらず、被害は甚大でした。
この原因として、多くの人々が気象現象への関心が薄く、災害を「自分事」として捉えていなかったことが挙げられます。どれだけ正確で有用な情報が発信されても、受け手が無関心であれば、その情報は防災に活かされず、結果として災害被害が減少しないという悲劇的な現実が浮き彫りになっています。
日本の豪雨災害は、地球温暖化による気象変動と、情報への人々の無関心という二つの大きな課題に直面しています。予測技術の向上だけでは、被害を減らすことはできません。豪雨は「いつでもどこでも」起こり得る現実として、私たち一人ひとりの防災意識の向上が不可欠です。
参考文献
- 立花義裕. (出版年不明). 『異常気象の未来予測』. 出版社不明.