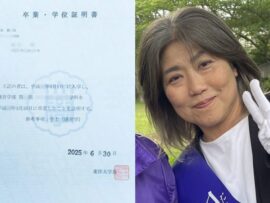第二次世界大戦末期、日本への原爆投下は、戦争を早期に終結させ、連合国側の犠牲を最小限に抑えるための「必要悪」であったという見方が、米国を中心に長く認識されてきました。しかし、この歴史的解釈に対し、戦争終結論を専門とする千々和泰明氏は疑問を呈しています。核兵器の使用という極めて重大な決断の前に、本当に「あらゆる手段」が尽くされたのか。本稿では、千々和氏の著書『誰が日本を降伏させたか 原爆投下、ソ連参戦、そして聖断』(PHP新書)の一部を再編集し、原爆投下の戦略的背景と、その「正当性」に関する多角的な視点を探ります。
 長崎の浦上天主堂が原爆投下により破壊された様子(1945年12月)
長崎の浦上天主堂が原爆投下により破壊された様子(1945年12月)
戦争終結時期に関する米英の認識と犠牲者最小化への模索
ポツダム会談では、首脳会談と並行して開催された米国と英国の連合参謀本部会合において、日本の組織的抵抗が終結する予定時期が「1946年11月15日」とされていました。これは1945年ではなく、実際の終戦よりも1年3カ月も長く、米国と英国は戦争が長期化することを想定していたことがうかがえます。
連合国側からすれば、この長期戦の間に、さらに多くの連合軍兵士が犠牲となり、捕虜やアジア太平洋地域の非戦闘員の命が危険にさらされ続けるという懸念がありました。一方で、日本軍国主義の脅威を根絶するためには、無条件降伏という方針からポツダム宣言以上に譲歩することは不可能であるという認識も共有されていました。このような状況下で、米国は自らが掲げる条件の下で早期に戦争を終結させ、かつ自軍の犠牲を最小限に抑えるため、「あらゆる手立て」を講じようとしたのです。その具体的な手段として、核兵器の使用とソ連の対日参戦が選択肢として浮上しました。
核使用とソ連参戦:優先された戦略的選択肢
米国が早期戦争終結のために講じようとした「手立て」は、核使用とソ連参戦でした。核兵器のみで日本を降伏させることができればそれに越したことはないものの、核使用には不確実性が伴うため、ソ連参戦も有効な選択肢として保持しておく必要がありました。これらの戦略的手段は、核使用によって引き起こされる人道問題よりも優先して考慮されたと見られています。
このように考えると、米国の核使用の目的が、日本との戦争を早期に終結させることによって、もし核を使用しなかった場合に発生したであろう甚大な犠牲を回避するためだった、とする「コスト最小化説」自体には、重大な疑いを差し挟むことは難しいように思えます。しかし、このコスト最小化説が、戦後の国際秩序を見据えてソ連に対する外交的威嚇を意図したとする「核外交説」よりも妥当性が高いとしても、それがそのまま核使用の正当化へと繋がるわけではない、と千々和氏は指摘します。
コスト最小化説と核使用の正当性への問い
核使用の正当性を本当に確立するためには、実際に核兵器が使用されたことで、どれだけ早期の戦争終結に繋がったのかという「効果のレベル」での徹底的な検証がなされなければなりません。そして、その検証に先立って、さらに重要な問いが残ります。それは、「コスト最小化のための手段として、核使用以外の選択肢は他に存在しなかったのか?」という根源的な問いです。
原爆投下という歴史的事実には、単純な答えでは片付けられない複雑な背景と多層的な議論が存在します。戦争終結を巡る米国の戦略的意図は、犠牲者最小化という大義名分のもとで展開されましたが、その選択肢が本当に最善かつ唯一のものであったのかという問いは、現代においても私たちに深く問いかけ続けています。この問いを追求することは、過去の出来事から学び、未来の国際社会における平和と安全を考察する上で不可欠な視点を提供します。
参考文献
- 千々和泰明『誰が日本を降伏させたか 原爆投下、ソ連参戦、そして聖断』PHP新書