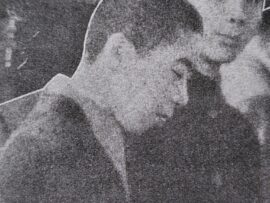漫画やアニメの世界に頻繁に登場する「関西弁キャラ」は、その独特の話し方や性格で親しまれています。「おしゃべり好き」や「食通」といったイメージで描かれることが多い彼らに対し、読者はどのような印象を抱いているでしょうか。大阪出身の日本語学者、金水敏氏は、関西弁キャラに共通する「7つの性質」を挙げ、これらのイメージが「一度に形成されたものではなく、歴史的に波状的に築かれてきた」と指摘しています。
役割語としての関西弁キャラとは
金水氏は、著書『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』の中で、特定のキャラクター(属性)に応じて話し方が決まる「役割語」という概念を提唱しています。例えば、「そうじゃ、わしが知っておるんじゃ」は老人、「そうですわよ、わたくしが存じておりますわよ」はお嬢様といった具合です。方言もまた、時にこの役割語として機能し、大阪弁や関西弁のキャラクターはその典型とされます。金水氏の分析によると、関西弁キャラには以下の7つの性質が共通して見られます。
- 冗談好き、笑わせ好き、おしゃべり好き
- けち、守銭奴、拝金主義者
- 食通、食いしん坊
- 派手好き
- 好色、下品
- ど根性(逆境に強く、エネルギッシュにそれを乗り越えていく)
- やくざ、暴力団、恐い
関西弁キャラに共通する「7つの性質」とその歴史的背景
これらの個性的なイメージは、どのようにして形成されてきたのでしょうか。金水氏は、その歴史的背景を詳細にひも解いています。
江戸時代の上方文化に由来するイメージ
上記の1から4、すなわち「冗談好き」「けち」「食通」「派手好き」といった性質は、主に江戸時代の上方文化、特に商都大坂(現在の大阪)の文化に由来すると考えられています。江戸の人々から見れば、大阪から来る商人たちは話好きで商売上手であり、食べ物や服飾といった現世的な快楽を素直に肯定する傾向が強かったため、これらのステレオタイプが生まれたのでしょう。
好色・下品な側面とど根性の形成
5の性質である「好色、下品」については、井原西鶴の「好色もの」に萌芽が見られますが、現代に繋がるイメージ形成には今東光や野坂昭如の作品が大きな影響を与えたとされます。
 大阪のシンボルである通天閣。関西弁キャラのイメージが語られる背景にある大阪文化を象徴する建造物。
大阪のシンボルである通天閣。関西弁キャラのイメージが語られる背景にある大阪文化を象徴する建造物。
また、6の「ど根性」は、例えば織田作之助の「夫婦善哉」の主人公・柳吉がど根性とは対極の人物であることからもわかるように、元来の大阪人のステレオタイプではありませんでした。これは、花登筐の「根性もの」作品が強い影響を与えたと推測されます。花登筐は、むしろ近江商人の気質を念頭に置いて作品を書いていたようです。
やくざ・暴力団のイメージの確立
最後の7、「やくざ、暴力団、恐い」というイメージは、江戸時代には上方者が柔弱と捉えられており、けんかっ早い江戸っ子とは対極と見られていた節があります。しかし、人形浄瑠璃「夏祭浪花鑑」のように、大阪の侠客の暴力を描いた作品は、後のやくざ・暴力団ものの先駆けとも言えます。そして、本格的なイメージ強化は、今東光の『悪名』シリーズ、1975年頃以降の暴力団映画、『嗚呼!! 花の応援団』『じゃりン子チエ』などの漫画作品によって進められたと考えられます。
昭和の古典的関西弁キャラに見る典型例
関西圏外を舞台にした作品に登場する典型的な関西弁キャラは、まさにこれらの性質を体現しています。昭和時代の作品に登場する彼らは、今日に続く関西弁キャラの「古典的」な例として、そのイメージ形成に深く関わってきました。
まとめ
金水敏氏による分析は、漫画やアニメに登場する「関西弁キャラ」が持つ多様なステレオタイプが、単なる思い込みではなく、江戸時代からの上方文化、そして近現代の文学やメディアの影響を複合的に受けながら、歴史的に段階的に形成されてきたことを明らかにしています。これらの「役割語」としての性質を理解することは、日本の地域文化やメディア表現の深層を読み解く上で非常に有益な視点を提供します。
参考文献
- 金水敏 著, 『大阪ことばの謎』, SBクリエイティブ, 2025年
- 金水敏 著, 『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』, 岩波書店, 2003年 (引用元記事に記載はないが、関連著書として補足)