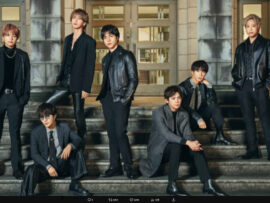近年、日本各地で頻発する豪雨災害や内水氾濫は、都市生活者の「移動」や「避難」のあり方を見直すことを迫っています。水害リスク軽減策の一つとして、今「浮く」技術が注目されています。これは環境変化に適応し続ける新しい暮らし方であり、日本でもその萌芽が見られます。本稿では、住宅、自動車、そして人間に関わる「浮く技術」の最前線を前後編で掘り下げます。前編では、その革新的な思想と具体的なメカニズム、そして世界の先進事例をご紹介します。
オランダにおける水との共生:歴史とパラダイムシフト
国土の約4分の1が海面下のオランダは、干拓地「ポルダー」を築き、「水との戦い」を続けてきました。しかし、度重なる大規模水害と地球温暖化の影響を受け、発想を転換。「水を押し返す」のではなく「水に浮かぶ」道を選びます。
アムステルダムでは既に運河に水上住宅が実現しており、建築家コーエン・オルトゥイス氏は「水は脅威ではない。チャンスだ」と語り、「水に浮かぶ都市」構想を提唱。これは気候変動時代の都市設計におけるパラダイムシフトを示しています。
 アムステルダムの運河に浮かぶ住宅群。水害対策と新しい都市生活の形を示す、環境適応型の水上建築の例。
アムステルダムの運河に浮かぶ住宅群。水害対策と新しい都市生活の形を示す、環境適応型の水上建築の例。
巨大な建物が水に浮かぶメカニズム:浮力の原理
そもそも、なぜ巨大な建物が水に浮かぶことが可能なのでしょうか。その鍵は、物理学の基本的な原理である「浮力」にあります。浮力とは、水中物体が水から受ける上向きの力です。古代ギリシャの科学者アルキメデスが発見した「アルキメデスの原理」によれば、この力の大きさは「物体が押しのけた水の重さ」と等しくなります。
つまり、物体の体積が大きければ大きいほど、押しのける水の量が増え、結果として大きな浮力を得られます。これにより、材質が水より重くても、体積の工夫次第で巨大な船や建築物でも水に浮かぶことが可能となり、「浮く技術」の科学的根幹を成しています。
結論
オランダの事例が示すように、「水は脅威ではなくチャンス」という発想は、気候変動下の都市設計に新たな道を開いています。この「浮く技術」は、日本が直面する水害問題への効果的な適応策としても期待されています。次編では、この先進技術が住宅、自動車、個人の命を守る道具としていかに応用・進化しているかを掘り下げます。