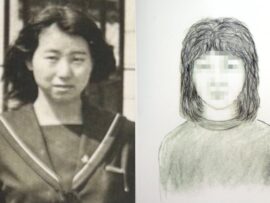8月1日。新潟県長岡市にとっては特別な日だ。
1945年の同日午後10時半、米軍B29爆撃機の編隊が来襲し、市街地の8割を焼き尽くした。市内への爆撃では分かっているだけでも1489人が犠牲になり、当時の人口からすると1000人に約20人が亡くなった計算だ。長岡市では毎年8月1日に犠牲者を悼み、平和を祈る催しが早朝から夜まで続く。あれから80年が過ぎた今年も多くの人が参加した。
神社の防空壕は役に立たなかった
午前6時、平潟公園。
地続きになっている平潟神社の主催で「戦災殉難者慰霊祭」が始まった。
戦時中、同公園は平潟神社の境内になっていて、「防空壕が二つ、もしくは三つ掘られていたと話す人もいます」(同神社)。あの夜、一帯は米軍B29爆撃機が雨のように投下した焼夷弾で炎に包まれた。防空壕は役に立たず、むしろ中に避難していた人々は逃げ場を失って、多くが命を落とすことになった。
境内では他の場所でもたくさんの人が亡くなった。例えば、現存する忠魂碑の周囲では炎で熱くなった碑の石に押しつけられるようにして死んでいた人もいた。「遺体を収容する時に皮が引っついてなかなかはがれなかったとも言われています」(同)。
こうして平潟神社の境内では市内で最も多い297人が犠牲になった。
そこで敗戦から13年が経過した1958年、「境内の一角に慰霊塔を建てよう」という運動が起き、寄附や市、県の補助で「戦災殉難者慰霊塔」が完成した。現在は平潟神社の旧境内の一部が公園化された場所にある。
80年目の慰霊祭には、遺族をはじめとして、磯田達伸市長や市民ら100人近くが訪れた。「旧満州で祖母の兄が戦死した。子供に戦争で何が起きたかきちんと伝えたい」と話す34歳の女性も小学4年生と4歳の子を連れて来ていた。
焼け野原をさまよった身元不明者たちの遺骨
それから1時間後の午前7時、1kmほど離れた昌福寺で長岡市仏教会の「戦災殉難者墓前法要」が営まれた。
この寺にもまた悲惨な歴史がある。墓地の一角に「戦災殉難者之墓」があり、平潟神社などで亡くなった身元不明者が埋められている。
身元不明の遺体は当初放置された。やむなく合同で荼毘(だび)に付されたが、遺骨の埋葬場所が見つからなかった。一時は全焼した市役所の仮庁舎が置かれた国民学校(現在の小学校)の屋内運動場に安置されたが、そのままにしてはおけない。市は焼失を免れた寺にいくつか打診したが、被災による財政逼迫で墓地の借地料が払えず、職員らは途方に暮れた。