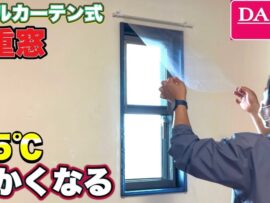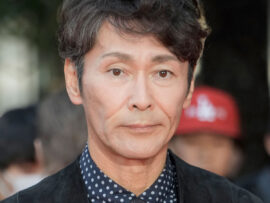「お金がすべてなのか、それとも人とのつながりが最も重要なのか?」──長年にわたり議論されてきたこの永遠のテーマは、私たちが幸せを求めながら命をつないできた人類の歴史を辿ることで、その答えのヒントが見えてきます。本稿では、小林武彦氏の著書『なぜヒトだけが幸せになれないのか』(講談社)から一部を抜粋し、人類が「幸せ」を感じる条件と、その概念がいかに変化してきたかを深掘りします。
 お金と人間関係、どちらが幸せの鍵か悩む人々のイメージ。人類の幸福の探求を表す
お金と人間関係、どちらが幸せの鍵か悩む人々のイメージ。人類の幸福の探求を表す
狩猟採集時代:命をつなぐことが「幸せ」だった日々
約700万年におよぶ人類の進化史の大部分は、狩猟と採集、そして移動の歴史でした。この時代、ヒトは常に「より良い」生存を目指し、技術を進歩させてきました。しかし、その暮らしは自然の猛威に左右され、常に危険と隣り合わせ。乳幼児の死亡率も高く、現代とは比較にならないほど「死」との距離が近かったと推測されます。この頃の「幸せ」とは、基本的に「食うこと、食われないこと、そして集団から追い出されないこと」を指しました。つまり、普通に暮らせることが、それだけで十分に幸福だったのです。
農耕と定住がもたらした「安定」と「新たな課題」
およそ1万年前から農耕が始まると、人類の状況は劇的に変化します。これは「ベター」な選択であり、多くの恩恵をもたらしました。
食料の安定と人口増加
まず、不安定な収穫に頼る狩猟採集生活に比べ、農耕は食料供給に大きな安定をもたらしました。さらに、移動生活から定住へと移行したことも特筆すべき変化です。定住化は、移動が困難な乳幼児、妊婦、高齢者にとって多大な恩恵をもたらし、結果的に人口の増加を促しました。
「所有」の概念と貧富の差の始まり
私が最も大きな変化と考えるのは、定住化によって「財産」を持てるようになったことです。住居を構え、食料をはじめとするあらゆるものを溜め込み、「所有する」ことが可能になったのです。当初は共同で畑を所有する形も見られましたが、本来「より良い」ものを求めるヒトの性質から、より多くの食料を溜め込む者が現れ始めます。溜め込むことは安心感を与え、「死からの距離」を遠ざけるため、「幸せ」につながると考えられたからです。これにより、「持つ者」と「持たざる者」、いわゆる「貧富の差」が生じ始めました。
安定の代償:格差と希薄な人間関係
農耕と定住によって生活の安定は得られましたが、その代償として新たな問題も発生しました。普段平和な時期は「キリギリス的」な生き方でも問題ありませんが、天災や悪天候が続くと、より多くを溜め込んだ「アリ的」なヒトが圧倒的に有利になります。十分に溜め込んでいなかった「キリギリス的」なヒトは、「アリ的」な裕福な者から食料などを借りるようになり、これが貧富の差をさらに拡大させました。やがてこの差は逆転不可能なレベルにまで広がり、階級制度へと進展していきます。
加えて、農耕社会では、狩猟時代のような集団でのマンモス狩りや情報共有といった協力的な行動が減少します。人々がお互いに力を合わせる機会が減り、人間関係が希薄になっていったのです。
「幸せ」の再定義:承認欲求とコミュニティへの貢献
食料を溜め込み裕福になったヒトは「死からの距離」が大きくなるため「幸せ」だと考えられがちです。では、世界で一番裕福な人が世界で一番幸せなのでしょうか?しかし、現実はそんなに単純ではないことは、私たちも知っています。このことは、「幸せ」が「死からの距離が保てている状態」という定義だけでは捉えきれないことを示唆しています。
当時、より多くの分け前を得ることは、その者がコミュニティに対して高い貢献度を示した証でした。つまり、その人の働きがコミュニティ全体の「幸せ」に貢献していたのです。ですから、「自分はこれだけ稼いだ、すごいだろう」と見せびらかすことは、本来問題のない行為でした。他者に承認されたいという「承認欲求」も然りです。その人の働きがみんなに還元されている以上、感謝され、褒められるのは当然であり、自慢する行為も許容されました。自慢は本来、自慢する本人も、それを聞く周囲の人も「幸せ」を感じ、共感できる「遺伝子に刻まれた行為」だったのです。
本稿は、人類が進化の過程でいかに幸福の概念を変化させてきたか、特に農耕と定住がもたらした光と影に焦点を当てて解説しました。現代社会における「お金」と「人とのつながり」という二項対立の根源には、こうした歴史的背景が深く関わっていると言えるでしょう。私たち自身の「幸せ」を考える上で、人類の歩みを振り返ることは、重要な示唆を与えてくれます。
参考文献
- 小林武彦『なぜヒトだけが幸せになれないのか』講談社、2025年。