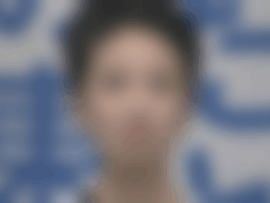[ad_1]
1995年の阪神・淡路大震災では、亡くなった犠牲者の6割が「女性」でした。「年齢・性別」ごとにみると最多は「70代女性」、次いで「60代女性」「80代女性」「50代女性」と続きます(出典:兵庫県「阪神・淡路大震災の死者にかかる調査について」など)。
【画像】生活保護の不正受給の内訳(2023年(令和5年)度)
これは単なる偶然ではありません。上記調査によれば死者のうち72.57%が、家屋が倒壊しその下敷きになったことによる「圧死」です。被災地に一人暮らしの高齢女性が多く、戦前・終戦直後に建てられた老朽家屋に住む人の割合が高かったと指摘されており、住環境のぜい弱さと、社会構造の問題があぶり出された結果と見ることができます。
そして今も、日本社会は根本的に変わっていません。厚生労働省「被保護者調査」によれば、生活保護を受けている世帯の約55%が65歳以上の高齢者世帯であり、その中でも特に単身女性の割合が高くなっています。
75歳を超えると、その傾向はさらに顕著になり、「老後にひとり取り残された女性たち」が次々と生活保護の窓口に訪れている現実があります。(行政書士・三木ひとみ)
家庭という名の「無報酬労働」が引き起こす貧困
「男は外で働き、女は家で家事・育児・介護。その果てにどちらも生活困窮。そんな人生の落とし穴に、誰が、どの瞬間に落ちてもおかしくないのです。
専業主婦として家族を支え、気づけば年金はほとんどもらえない。そんな女性たちをたくさん見てきました」
そう語るのは、阪神・淡路大震災以前から、神戸で女性支援を続けてきた田坂美代子さん。「DV」という言葉が知られていなかった頃から30年以上にわたり、困窮する女性たちと向き合ってきました。
「彼女たちは、働かずに年金を払ってこなかったのではありません。『家庭』という名の『無報酬労働』に従事してきたのです」
わが国ではよく「自己責任」という言葉が口にされます。しかし、このような境遇を「自己責任」で片付けることはとうてい不可能です。
[ad_2]
Source link