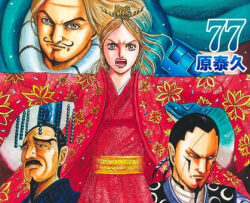全国的にクマによる農作物被害や人身事故が増加する中、8月14日には北海道の知床・羅臼岳で男性登山客がヒグマに襲われ命を落とす痛ましい事故が発生した。毎年報じられるクマの「人里出没」ニュースは、もはや夏場の恒例行事。一体、この事態の背景には何があるのか、そして私たちはどう向き合うべきだろうか。
ヒグマ生息数増加と「人慣れ」の要因
北海道環境生活部のヒグマ対策室担当者は、人里出没の原因を「生息地域でのエサ不足、個体数の増加、人に対する警戒心の希薄化」と説明する。かつて個体数減少が懸念され1990年に廃止された「春クマ駆除」の結果、1990年の推定5,300頭から2022年には約2.3倍の12,200頭に増加し、生息域も拡大した。現在、担当者は出没が社会問題化していなかった時期の個体数に戻すべく、個体数管理を進めていると述べる。
「ゾーニング管理」による人とクマの生活圏分離
本来臆病なクマが人里へ下りてくるのはなぜか。担当者は、観光地などで人間が誤ってエサを与えることで「人慣れ」が進み、人間との距離感が縮まったケースを指摘する。一度人間の食べ物の味を覚えると、その味を求めて人里のゴミをあさる可能性もあるため、北海道では「ゾーニング管理」という方法で生活圏を分離。市街地や農業地域を「排他地域」「防除地域」とし、生息地との間に「緩衝地帯」を設けて管理捕獲や個体数管理捕獲を実施し、被害を未然に防ぐ方針だ。
 市街地に出没する可能性のあるヒグマのイラスト
市街地に出没する可能性のあるヒグマのイラスト
駆除を巡る課題と社会全体の共存への模索
クマの駆除を巡る世間の声は、「殺すなんてかわいそう」という感情論と、地域住民の命に関わる問題という現実の間で揺れ動く。人間に危害を加える場合の捕獲はやむを得ないが、北海道は駆除を避けるためにもゾーニング管理など共存を考えた施策を進めている。担当者からは、駆除への感情的な意見が多く、理解を得る難しさも語られたが、丁寧な説明を続けることの重要性を強調。自然保護と人々の安全な生活圏保全、この二つの両立が今後の大きな課題となる。
増加するクマの出没は、生息数の回復と人間活動の拡大が複雑に絡み合った社会問題だ。北海道のゾーニング管理や個体数管理は有効な対策だが、感情論を超え、社会全体でクマの生態を理解し、安全な共存を目指す姿勢が求められる。人間と自然が持続可能な関係を築くため、包括的な戦略と粘り強い対話が不可欠である。
参考文献
出典: https://news.yahoo.co.jp/articles/be57ecc8e5ba56e90d6d5b045fe0c16d3da0ec56