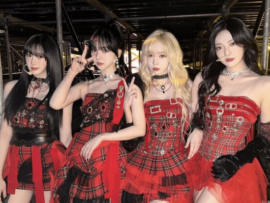たくさん寝ているはずなのに、なぜか疲れが取れない――。そんな経験はありませんか?現代社会において、単なる休息では回復しきれない「深い疲れ」を抱える人が増えています。「朝から体がだるい、重い」といった疲労感の裏には、私たちの体が発する重要なサインが隠されています。延べ50万人以上の患者を診てきた脳神経外科医が、その疲労の正体と、見過ごされがちな「脳の疲れ」について詳しく解説します。
 休息しても取れない疲労の原因を探るイメージ写真
休息しても取れない疲労の原因を探るイメージ写真
疲れには「体の疲れ」と「脳の疲れ」がある
皆さんはどんなときに「疲れた」と感じるでしょうか。例えば、フルマラソンを走り終えた後や、一日中外回りの仕事で歩き続けた日の終わりには、誰もが「疲れた」と感じるはずです。このように、体を酷使した後に感じるのは、肉体的な疲労、すなわち「体の疲れ」と呼べます。関節や筋肉の痛みや張りとして現れることも少なくありません。
一方で、体を激しく動かしていないにもかかわらず、疲れを感じることも多々あります。長時間デスクワークに集中した時、気の合わない相手と話し続けた時、大勢の前でスピーチをした時、あるいは子どもの試合や発表会を見守った後など、どっと疲れが押し寄せ、「あー、疲れた」とつぶやく経験はないでしょうか。頭がクラクラしたり、呼吸が乱れたりすることもあります。これらは精神的な疲労、すなわち「脳の疲れ」です。疲れは大きくこの二つの種類に分けられることをまず理解しておきましょう。体や脳を使いすぎた結果として生じるのが、疲労の根本的な原因なのです。
「脳の疲れ」はさらに「自律神経の疲れ」と「心の疲れ」に細分化される
「脳の疲れ」は、さらに細かく「自律神経の疲れ」と「心の疲れ」の二つに分類することができます。自律神経の疲れは、自律神経のバランスが乱れることによって引き起こされます。自律神経は意識してコントロールできないため、原因がはっきりしないまま、無意識のうちに疲労感を感じるのが特徴です。
一方、「心の疲れ」は、嫌なことや面倒なことによるストレスが原因で生じます。自律神経の疲れが無意識的であるのに対し、心の疲れは意識することができ、感情を伴う点が特徴です。このように、疲労は大きく分けて体の疲れと脳の疲れの2種類、さらに詳しく見ると3種類に分けられます。現代社会では、昔に比べて体を動かす機会が減り、肉体的な疲労を感じにくくなった反面、精神的な負担が増大し、「脳の疲れ」(自律神経の疲れや心の疲れ)に悩まされる人が増加傾向にあります。
現代社会が引き起こす「脳の疲れ」の増加
現代は、コンピューターやロボットが多くのタスクをこなしてくれる便利な世の中です。洗濯板で手洗いしていた時代から、今は洗濯機のボタン一つで「洗濯・脱水・乾燥」まで完了するようになりました。これにより、私たちは肉体労働から解放され、体の疲れを感じる機会は減少しました。しかしその一方で、情報過多、複雑な人間関係、そしてスマートフォンやSNSの普及は、私たちの脳と自律神経に新たな負担をかけています。異常気象のような環境変化もまた、自律神経のバランスを狂わせる要因となり得ます。
こうした要因が、現代人が抱える「脳の疲れ」の背景にあるのです。効果的な休息を取り、脳の疲労を回復させることが、健康的な生活を送る上でこれまで以上に重要になっています。