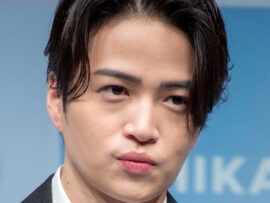就職活動の面接において、学生の言葉は一見すると似通っているように聞こえることがあります。「リーダーシップを発揮しました」「問題解決能力を培いました」といった、多くの学生が口にするフレーズは、聞き慣れた表現かもしれません。しかし、面接官は同じ言葉であっても、ある学生には「この人は本当に賢い」と感銘を受け、別の学生には「もしかしたら、表面を取り繕っているだけではないか」と感じてしまうことがあります。この評価の差は一体どこから生まれるのでしょうか。
面接官が「賢い」と感じる学生の特徴
就職面接で「賢い」と評価される学生は、単に知識が豊富であるとか、話が華やかであるという理由だけではありません。面接官が本当に注目しているのは、学生がどれだけ深く物事を「考え抜いた跡があるか」です。例えば、最新のニュースから得た情報を並べる学生は、一見すると勉強熱心に見えるでしょう。「AIの未来が重要だと思います」「御社は成長産業だから志望しました」といった発言も、表面的には立派に聞こえます。
 面接で語る学生と聞く面接官の様子
面接で語る学生と聞く面接官の様子
しかし、面接官が「具体的にどのような経験からそう思ったのですか?」と問いかけると、途端に言葉に詰まってしまうケースがあります。これは「賢そうに見えて実は浅い」という典型的な例です。このような学生は、インターネットや書籍で得た情報をそのまま反復しているだけで、自分自身の頭で深く掘り下げて考えていないことが露呈してしまいます。
本当に賢い人と「浅い」人、たった一つの決定的違い
一方で、面接官に「本当に賢い」という印象を与える学生は、どんなに些細な経験であっても、それを自分自身の頭で咀嚼し、そこから得た気づきや学びを筋道を立てて語ることができます。アルバイト先での失敗談や、部活動での人間関係の悩みといった、一見すると「平凡な体験」であっても、その経験を通じて「なぜ自分はそう考えたのか」「どう工夫して状況を改善したのか」といった思考のプロセスを具体的に示すことで、面接官に強い印象を残すのです。
この違いを生み出す核となるのは、「問いを持てるかどうか」という能力です。「浅い」と見なされてしまう学生は、あらかじめ用意された「正解らしき答え」を語ろうとします。「御社で成長したいです」「社会に貢献したいです」といった言葉は耳障りが良いものの、誰が言っても同じに聞こえてしまい、その学生ならではの個性や思考力を伝えるには不十分です。
面接官を納得させる「なぜなぜ分析」思考術
面接官に「賢い」と評価される学生は、自身の経験を通して、常に自分なりの「なぜ」を問いかけています。例えば、授業に遅刻してしまったという出来事があったとします。一般的な学生であれば、「夜更かししたから早く寝よう」といった表面的な解決策で終わってしまうかもしれません。しかし、深く考える学生は、以下のような「なぜなぜ分析」を行います。
- なぜ授業に遅れたのか? → 朝起きるのが遅かったから。
- なぜ朝起きるのが遅かったのか? → 夜更かししたから。
- なぜ夜更かししたのか? → スマートフォンを触っていて寝る時間が遅くなったから。
- なぜ夜にスマートフォンを触ったのか? → 特にやることがなかったから、動画を見ようと思った。
このような深掘りされた思考プロセスを通じて、「夜更かししたのはやることがなかったからだ。それなら、夜はスマートフォンのロックをかけて読書する時間にしよう」といった、根本的な原因に基づいた解決策にたどり着くことができます。面接官は、このような多層的な思考を披露する学生に対して、単なる知識の有無ではなく、「自分の頭で深く考えられる人」としての可能性を感じ取るのです。新刊『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』の著者である藤井氏も、自身の経験からこの「考え抜く力」の重要性を強調しています。
面接における「賢さ」とは、知識の羅列ではなく、自分自身の経験を深く考察し、論理的な思考プロセスを通じて本質的な課題を発見し、解決策を導き出す能力に他なりません。この「考え抜く力」こそが、面接官が本当に求める「賢さ」であり、内定への扉を開く鍵となるでしょう。
参考文献:
- 藤井 雅人. 『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』. 著書内記述.
- Yahoo!ニュース (2025年9月1日). 面接で「賢い」と感心される人と「実は浅いんじゃないか」とがっかりされる人、その差は一体どこにあるのでしょうか。. https://news.yahoo.co.jp/articles/b1dcf5762b7019825ea9dcd5021bf096fc70d976