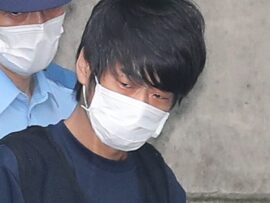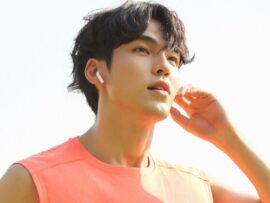近年、日本の山間部だけでなく、人里におけるツキノワグマの襲撃被害が急増し、深刻な社会問題となっています。特に東北や北関東では、農作業中や自宅にいる住民が襲われる事例が相次ぎ、人々の生活を脅かしています。冬眠を控えるこの時期、クマが餌を求めてさらに人里に出没する可能性が高まっており、林野庁や地方自治体は住民に対し、警戒を呼びかけています。この異例の事態の背景には、クマの生息環境で観測されている特定の現象が深く関わっています。
全国で続くクマの人身被害:この10年で最多ペースを更新
環境省の報告によると、今年4月から7月にかけて全国で発生したクマによる人身被害は55件に上り、これは過去10年間で最も多かった2023年度の同期56件に匹敵するハイペースです。8月には福島市や秋田県大館市で負傷者が出る事故があり、さらに8月31日には群馬県嬬恋村で渓流釣りをしていた男性が顔に大けがを負うなど、被害は続いています。
残念ながら、命を落とすケースも複数発生しています。7月4日には岩手県北上市で自宅に侵入したクマに81歳の女性が襲われ死亡、7月31日には北秋田市の障害者施設で73歳の入所女性が犠牲となりました。これらの事例はいずれも、普段から人々が生活する日常圏内で起きており、住民の不安が募っています。
人里出没の背景にある「ブナの実の大凶作」と「親子グマの増加」
クマが人里に頻繁に出没する主要な原因として、専門家は山林の餌資源の状況を指摘します。東北森林管理局の予測によると、今秋、東北地方のクマの主な餌となるブナの実が2年ぶりに「大凶作」となる見込みです。これは、現在の調査方法が導入された2004年以降で2度目の、調査対象となる東北5県(福島県以外)全てで大凶作が予測される異常事態です。ブナの実は豊作の翌年が凶作となり、およそ5~6年周期で豊作を迎えるサイクルがあります。
過去、大凶作であった2023年度には、全国で219件(死者6人)と、この10年で最多の人身被害が記録されました。その半数以上にあたる111件が9月と10月の2カ月間で発生しており、冬眠前の餌不足が人里出没を助長する傾向が明らかになっています。
森林総合研究所によると、ツキノワグマが人里や市街地に出現する頻度は、ブナやドングリ類の豊凶と密接に関連しています。特に、ブナの実が豊作だった翌年には「親子グマが人里に出没する可能性が高い」と指摘されています。これは、豊作の年に十分な栄養を蓄えたメスのクマが、冬眠中に仔を産むためです。2024年は青森県で四半世紀ぶりの豊作を記録するなど、各県で平年作または豊作となった地域もありました。
 日本の山林に生息するツキノワグマの親子(環境省提供写真)
日本の山林に生息するツキノワグマの親子(環境省提供写真)
個体数増加と生活圏の拡大:共存に向けた社会の取り組み
そもそも、クマの出没数は2000年頃から増加傾向にあり、それに伴い駆除数も増えています。クマ自体の個体数が増加している可能性が指摘されるとともに、その生息域も拡大していると考えられています。森林総合研究所は、クマと人間の生活圏が「隣接するようになってしまった」と警鐘を鳴らしています。
このような状況に対応するため、2024年9月1日には改正鳥獣保護管理法が施行されました。これにより、人の生活圏でクマやイノシシなどが出没した場合、市町村の判断で市街地でも猟銃の使用が可能になりました。クマによる襲撃は重傷を負う可能性が高く、命を落とす危険性もあります。森に暮らすクマと街に暮らす人々がどのように安全に共存していくか、社会全体の警戒と試行錯誤が今後も続くことになります。
参考文献
- 環境省 (Ministry of the Environment)
- 林野庁 (Forestry Agency)
- 東北森林管理局 (Tohoku Regional Forest Office)
- 森林総合研究所 (Forestry and Forest Products Research Institute)
- 毎日新聞 (Mainichi Shimbun)
- Yahoo!ニュース (Yahoo! News)