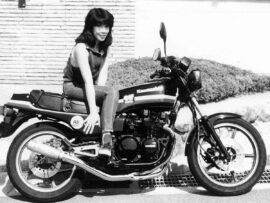日本が世界に誇る学校での水泳教育が、今、大きな転換期を迎えています。文部科学省の学習指導要領で必修とされているにもかかわらず、小中学校から水泳の授業、そしてそれを行う屋外プールが減少しつつある現状は、多くの関係者にとって看過できない問題です。特に、子供を持つ保護者や教育に携わる人々は、この変化を肌で感じていることでしょう。
私自身、中国の水郷地帯で育ちながらも、正しい泳ぎ方を学ぶ機会に恵まれませんでした。そのため、ほとんどの小中学校に屋外プールが設置され、子供たちが水泳を学ぶ日本の教育環境には、長年羨望の念を抱いてきました。私が暮らす新宿区の公共プールでは、日本の学校に通う子供は泳げても、その親である外国人が泳げないというケースも少なくありません。一方、日本人親子は共に真剣に泳ぐ姿が見受けられ、日本の水泳文化の浸透度を物語っています。中国では学校にプールがあること自体が稀で、水泳はオリンピック選手を目指すエリート教育の一部であり、「誰もが泳げるようになる」という発想とは異なるのが実情です。
日本における水泳教育の伝統と価値
日本では古くから水泳が重視されてきました。専門家によれば、海に囲まれ川も多い国土において、水泳はかつて武士が身につけるべき教養の一つであったとされています。現代の学校における水泳教育の普及は、1964年の東京オリンピック開催が大きな契機となり、1970年代には全国の学校にプールが設置されるようになりました。
子供たちが能力に関わらず泳ぎ方を学ぶという教育方針は、身体を鍛え、忍耐力を養う上で非常に優れたものです。水難事故の減少に貢献するだけでなく、国民全体の健康増進と長寿にもプラスに作用していることは間違いありません。私から見れば、学校の水泳授業はまさに文武両道を体現するものであり、日本式教育の真髄とも言えるべき存在です。
転換期を迎える学校プールと授業の現状
しかしながら、この伝統的な日本の水泳教育が今、岐路に立たされています。具体的には、屋外プールの設置率が近年、目に見えて減少しているのです。2018年には小学校の94%、中学校の73%に屋外プールがありましたが、わずか3年後の2021年には、小学校で87%、中学校で65%と、その割合は明らかに低下しました。
 日本の学校で行われる水泳の授業と、その伝統的な屋外プールの光景
日本の学校で行われる水泳の授業と、その伝統的な屋外プールの光景
水泳の授業自体が完全に廃止されるケースもあれば、学校外の公共プールを利用したり、民間のスイミングスクールに委託したりするなどの代替措置が取られることもあります。こうした変化は、学校の施設維持コスト、教員の負担、老朽化対策など、複合的な要因が背景にあると考えられます。
まとめ:変化の中で見直される日本の水泳教育の未来
日本の小中学校における水泳授業は、単なる体育科目ではなく、武士の時代から続く伝統文化、そして国民の安全と健康を守るための重要な教育として深く根付いてきました。しかし、屋外プールの減少という現状は、この長年の伝統が現代社会の様々な課題に直面していることを示しています。
この転換期にあって、日本の水泳教育がどのような形で存続し、未来へ引き継がれていくのか、その動向は日本の社会と子供たちの成長にとって、引き続き注目すべき重要なテーマとなるでしょう。
参考文献:
- Yahoo!ニュース. (2025年9月2日). ほとんどの小中学校に屋外プールがある日本。「泳げない人」の多い中国で育った私はずっと羨ましく思っていたが、この「日本の伝統」が転換期を迎えている. https://news.yahoo.co.jp/articles/2065d58e6d7ee88b2d892a7862144b1149b045e1