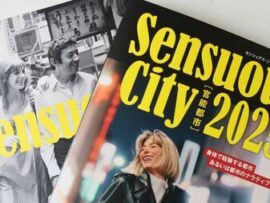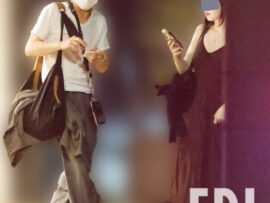元TOKIOの城島茂が、自身が直面した「ママ友会」での会計ルールを巡るエピソードを語り、芸能界と一般社会における金銭感覚の差が大きな話題となっています。年長者が支払うのが慣例とされる芸能界で長く活動してきた城島にとって、「割り勘」が当然とされるママ友会のルールは新鮮な驚きでした。この出来事は、現代日本社会における「支払い」に関する暗黙の了解や、人間関係における「気遣い」の多様性について改めて考えさせられる契機となっています。
城島茂が明かす「ママ友会の割り勘ルール」と妻の反応
2019年にタレントの菊池梨沙と結婚し、翌年に長男が誕生した城島茂は、2024年4月4日にMBSラジオ『アッパレやってまーす!』に出演。自身が体験した「ママ友会」での会計トラブルについて赤裸々に語りました。芸能界でベテランとして活躍する城島は、仕事の現場では年長者として食事代を奢ることが多いと明かし、「僕、年上の現場が多いんで、『ええよ』ってなるじゃないですか」と、その慣習に慣れ親しんでいる様子を伺わせました。
しかし、幼稚園の集まりやママ友のランチ会に妻の代わりに顔を出した際、いつもの感覚で「ああ、いいですよ」と全員分の会計を持とうとしたところ、後日、妻から強く叱責されたといいます。その理由は、「全部割り勘で決めているから」という、ママ友会独自の明確なルールにありました。妻は城島に対し、「変に(支払いを)やると、バランスが崩れるから」「ほかのお父さんたちのとき、また気遣うから。そこはきちんとみんな割ってるから」と説明。一人の行動がグループ全体の関係性に影響を与えかねないという、繊細な「気遣い」が背景にあったのです。この「社会の常識」に城島は驚きを隠せず、「(世の中はそう)なんですね」と振り返りました。
 ラジオ番組でママ友会での会計ルールについて語る城島茂
ラジオ番組でママ友会での会計ルールについて語る城島茂
芸能界と一般社会の「金銭感覚」の違いを鈴木拓・ビビる大木が解説
城島の体験談を受け、共演者のドランクドラゴン・鈴木拓とビビる大木も、芸能界と一般社会における会計文化の違いについて自身の見解を述べました。鈴木拓は城島の妻の意見に強く共感し、「社会というか、この業界以外だと本当にそうですよね」「絶対、そうですよ。それが社会です」と断言。芸能界以外の環境では、「いい、いい。オレが払う」という行為が、かえって相手に気を使わせたり、グループ内の秩序を乱したりする可能性があると指摘しました。
ビビる大木もまた、独自のルールを明かしました。後輩と二人で食事に行く際は奢るものの、その後輩が家族を連れてきた場合は、それぞれ家族の分を出し合うというのです。「家族同士の付き合いはオール自分たち持ち」という線引きは、公私の区別と、それぞれの家庭の金銭感覚への配慮を示すものです。さらに大木は、「(奢られずに)払いたい」と意思表示する大人がいることにも言及。「自分の分も払って、オレはこの食事会に参加したい」という人々は、奢られることで生じるかもしれない「借り」や、不公平感を避け、対等な関係性を望んでいると解説し、多様な価値観が存在することを浮き彫りにしました。
「割り勘」が示す現代社会の「気遣い」と人間関係の構築
今回の城島茂のエピソードは、単なる支払い方法の問題に留まらず、現代日本社会における人間関係の構築と「気遣い」の複雑さを示唆しています。芸能界のような特殊な環境では、年長者が後輩に奢るという文化が根強く、それが一種の権威やリーダーシップの象徴となることもあります。しかし、ママ友会のような地域コミュニティや一般の社会生活においては、全員が公平に費用を分担する「割り勘」が、むしろ円滑な人間関係を維持するための重要なルールとなっています。
この「割り勘ルール」は、誰もが対等な立場で参加し、互いに余計な「気遣い」をさせないための配慮であり、特定の個人に負担や義理を感じさせないための工夫でもあります。特に、金銭感覚が多様化する現代において、不透明な会計ルールはストレスや誤解の原因となりかねません。城島茂が知らなかった「社会の常識」は、年齢や立場に関わらず、それぞれのコミュニティに根ざした暗黙のルールを理解し、尊重することの重要性を浮き彫りにしました。
結論
城島茂がママ友会で経験した「割り勘ルール」を巡る出来事は、私たちに社会における多様な金銭感覚と「気遣い」のあり方について深く考える機会を与えてくれました。芸能界と一般社会、あるいは異なるコミュニティの間には、それぞれ独自の慣習や暗黙の了解が存在します。良好な人間関係を築き、維持するためには、自分の常識を押し付けるのではなく、相手の立場やその場のルールを理解し、柔軟に対応する姿勢が不可欠です。今回のエピソードは、そうした社会の奥深さを改めて教えてくれるものでした。
参考文献
- ENCOUNT編集部. 「城島茂が「絶対、そうですよ。それが社会です」」 Yahoo!ニュース, 2024年4月5日. https://news.yahoo.co.jp/articles/dbb0e776343fe62671c88822b167d0581bfab733