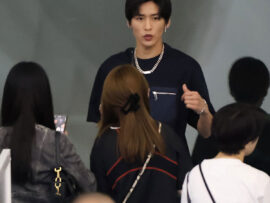現代の国際政治において、「反米」という共通項で結ばれる中国、ロシア、イラン、北朝鮮の四カ国が注目されています。しかし、かつての冷戦時代のような共通のイデオロギーは存在せず、その協力関係は個々の国同士の二国間レベルに留まっています。この複雑な関係性を深く理解し、それらの戦略的な利害の乖離を認識することは、「新冷戦」への移行を防ぐ上で極めて重要です。本稿では、これらの国家間の微妙な差異を分析し、国際秩序の安定に向けた多角的なアプローチを考察します。
中国の覇権戦略と中露関係の複雑性
中国は、米国との世界的な覇権競争において勝利を収めるという長期的な戦略を追求しています。この戦略の核心は、米国とその同盟国間の距離を広げ、これらの同盟国を中国の影響圏に引き込むことにあります。そのため、ロシアがウクライナ侵攻を行った際も、中国はロシアに対して積極的な支持や支援を控えました。これは、過度なロシア支持が欧州諸国をかえって米国側に押し出す結果となることを警戒したためです。また、ロシア自身も中央アジアにおける中国の影響力拡大に警戒感を抱いており、上海協力機構(SCO)が初期に果たした役割も、これら二つの競争国間の利害調整が主要な目的でした。
 「反米」を共通項とする中国、ロシア、イラン、北朝鮮の首脳たち
「反米」を共通項とする中国、ロシア、イラン、北朝鮮の首脳たち
朝鮮半島を巡る中朝間の戦略的相違
中国と北朝鮮の間にも、戦略目標における明確な違いが存在します。中国は朝鮮半島を含む周辺地域での平和と安定を強く望み、その上で韓国をはじめとする米国の同盟国を自国の味方に引き込む努力を続けています。これは、米国との覇権競争において有利な立場を築く上で不可欠であると考えているためです。一方、北朝鮮は核開発を通じて朝鮮半島での優越的地位を追求しており、この政策は朝鮮半島の安定を損なう可能性を秘めています。もし安定が損なわれれば、米軍が朝鮮半島、すなわち中国の近隣にさらに配備される事態を招きかねず、これは中国が最も望まない結果です。このような背景から、中国は現在も「朝鮮半島の非核化」の原則を堅持しています。北朝鮮とロシアの関係も、ウクライナ戦争の終結に伴い大きく変化する可能性が高く、北朝鮮は再び中国への傾斜を強めるでしょう。
「新冷戦」回避へ向けた多角的アプローチ
このような国際情勢が「新冷戦」へと発展する可能性を低減するためには、戦略的な外交努力が不可欠です。まず、米国は修正主義的な四カ国間の利害関係の違いに焦点を当て、より戦略的な外交を展開する必要があります。ウクライナ戦争の終結を急ぐ中でも、ロシアとウクライナの間で原則とバランス感覚を持って交渉を仲裁しなければなりません。原則を無視してロシアの休戦条件を一方的にウクライナに強要するようなことがあれば、修正主義勢力に勝利感を与え、彼らを勢いづかせることになります。
次に、米国は同盟国に対し、より大きな防衛責任を負わせる一方で、関税などの経済的圧迫や力の論理で追い詰めることは控えるべきです。そうしなければ、国際政治における米国の中心的な地位がさらに弱まる恐れがあります。第三に、中国との関係を安定させることも重要です。競争は避けられないとしても、ゲームのルールを明確にし、ある程度予測可能な関係を構築するよう努めるべきです。
最後に、米国以外の西側諸国、そして民主主義と規範に基づいた国際秩序の持続を望む国々は、相互の連帯を強化し、国際秩序が力に任せた無秩序へと変質するのを防ぐために力を合わせる必要があります。日本をはじめとするこれらの国々は、米国が手が回らない国際公共財の生産に貢献するリーダーシップを発揮することが求められています。
尹永寛(ユン・ヨングァン)/元外交通商部長官、峨山政策研究院理事長