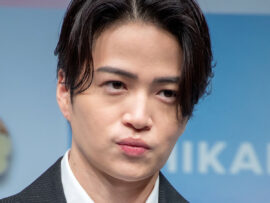9月に入っても各地で猛暑日が続くなど、異常な暑さは収まる気配を見せず、日本全国の米農家が未曽有の窮地に立たされています。今年の7月の降水量は平年のわずか13%という記録的な少なさで、水不足は収穫を目前に控える田んぼに深刻な影響を及ぼしています。土は乾燥してひび割れ、稲が十分に育たないという事態が全国各地で相次ぎ、日本の食を支える新米の収穫期に大きな影を落としています。
 記録的猛暑と水不足で乾燥し、亀裂が入った日本の田んぼの様子
記録的猛暑と水不足で乾燥し、亀裂が入った日本の田んぼの様子
深刻化する水不足と収穫への影響
この記録的な水不足は、稲の生育に壊滅的な影響を与えています。田んぼの土はカラカラに乾き、深い亀裂が入り、稲の葉は茶色く変色して根元が腐っている様子も見受けられます。特に被害が深刻とされる石川県七尾市で広く田んぼを管理する「向田町集落営農組合」代表の花園陽一氏(67)は、現状について「収穫自体はできると思いますが、商品として出荷できるレベルまで育つかどうかはわかりません」と厳しい見通しを語ります。水が少ないため、米粒が割れてしまったり、小さな破片のような形で成長が止まったりする「不良品」が続出する懸念が現実のものとなりつつあります。収穫された米は、煎餅や米粉として加工するしかなく、正規の米として出荷する場合の販売価格の半分以下にしかならないため、農家が被る経済的なダメージは計り知れません。
干ばつに苦しむ田んぼの現状
FRIDAYデジタルの取材班が花園氏の管理する田んぼに足を踏み入れると、地面は干上がり、茶色く変色した稲が目立ちました。素人目にも、米の収穫が極めて困難であることが明らかです。花園氏によれば、今年の収穫量自体が昨年の3分の2ほどに減少する上、商品価値のある米として出荷できない「不良品」が多数出る見込みです。このような状況下で、農家は県の農業共済制度に頼らざるを得ません。この制度は、前年の売り上げに基づいて農家が加入割合を決定し、実際の収入が加入時の想定を下回った場合に、その差額が共済金として補填される仕組みとなっています。しかし、制度による補填だけでは、長期的かつ大規模な気象変動による被害を完全にカバーすることは難しいのが現状です。
農家の「危機感が感じられない」政府対応への不満
8月、当時の農林水産大臣であった小泉進次郎氏(44)は干ばつに苦しむ農家を視察し、「給水車を出します」と政府としての支援策を打ち出しました。しかし、現場の花園氏はこれに対し、「危機感がまったく感じられない」と強い憤りを隠しません。彼は、政府や県・市からの具体的な対策が何も打ち出されていないと指摘します。各集落が水源をいくつか保有しているものの、長引く猛暑と雨不足によりほとんどが干上がってしまい、この異常な暑さの中で作物を育てることの難しさを痛感しています。
さらに花園氏は、「そのくせ、政府は『米を安く売れ』なんて言い出す。何を言ってるんだと言いたい」と、政府の政策に対する不満をあらわにしました。彼は、消火栓を自由に使えるようにして水が足りない場所に散布するなど、より大胆で実効性のある対策が必要だと訴えます。「実際に米を作っていない人間には、この苦しみはわかりません」と、政策決定者と現場の農家との間に横たわる認識のギャップを強調しました。
結論
日本の食卓を支える米農家は、記録的な猛暑と深刻な水不足により、収穫量の激減と品質劣化という二重の困難に直面しています。現場からは、政府や自治体の対応に対し「危機感の欠如」や「具体的な対策の不足」といった厳しい声が上がっており、現在の支援策では不十分であるとの認識が広がっています。
日本の食料安全保障の根幹をなす米作りの現場が抱える悲痛な訴えに対し、政府はどのように向き合い、実効性のある、そして現場の苦しみに寄り添った支援策を講じていくかが、喫緊の課題となっています。今後の政策の動向が、日本の農業の未来、ひいては私たちの食生活に大きな影響を与えることは間違いありません。
参考文献
- FRIDAYデジタル
- Yahoo!ニュース (元記事リンク)