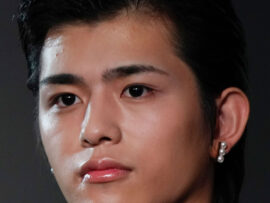かつて「大阪の台所」として親しまれ、地元住民で賑わった黒門市場が、外国人観光客を主なターゲットとした1本5000円の高額なカニの足などを販売するようになり、「ぼったくり商店街」と揶揄され、その評判を落としつつあります。この現象は、大阪を代表する観光地である道頓堀にも顕著に現れており、訪日外国人観光客、特に中国人観光客の増加が、街の様相を大きく変えつつあります。この急速な変化の背景には何があるのでしょうか。
 黒門市場で販売される高額なカニの足
黒門市場で販売される高額なカニの足
「大阪の台所」黒門市場の変貌と「ぼったくり」批判
黒門市場は、新鮮な魚介類や青果が手に入る場所として、長年大阪の食文化を支えてきました。しかし、近年、インバウンド需要の急増に伴い、観光客向けの露店が増加。特に、高級食材を高値で提供する店舗が目立つようになり、地元客からは「観光客向けに価格が吊り上げられている」「昔の活気が失われた」といった厳しい声が上がっています。一部では「ぼったくり」との批判も聞かれ、伝統的な市場としてのイメージに影を落としています。
道頓堀を歩く3人に1人は中国人:データが示す「中国化」の加速
東京・上野のアメ横と並び称される大阪の道頓堀もまた、劇的な変化の渦中にあります。道頓堀商店街には平日でも1日あたり約4万人もの人々が押し寄せ、コロナ禍による閑散とした時期を経て、現在では中国人観光客の増加により「毎日がお祭り騒ぎ」と、道頓堀商店会の上山勝也会長(63歳、取材当時)は喜びを語っています。
ドコモ・インサイトマーケティングの携帯電話位置情報に基づいた訪日観光客動態調査によると、道頓堀商店街周辺(1キロメートル四方)には、1カ月で約39万3000人、1日あたりに換算すると約1万3000人もの中国人観光客が訪れていることが判明しました。これは単純計算で、道頓堀を歩く人々の約3人に1人が中国人であることを意味します。銀座や浅草といった他の主要観光地を上回り、道頓堀は現在、全国で最も中国人観光客が密集するエリアの一つとなっています。
中国人観光客向けに「変容」する商店街の風景
こうした訪日中国人客を主なターゲットとする道頓堀商店街では、街の「中国化」が急速に進んでいます。観光客で賑わう戎橋の中心部から東へ向かって歩くと、「(中国)大連の味」や「中華物産」といった中国語の看板が目につくようになります。大手ドラッグストアである「ツルハ」の看板も、このエリアでは中国語表記の「鶴羽薬妝店」へと変化しています。通りには小規模な露店がせり出し、店舗の店員も中国人であることがほとんどです。これは、中国人観光客の購買行動やニーズに特化した店舗が増え、街の景観やサービス提供者の構成までが変容している状況を示しています。
結論
黒門市場の「ぼったくり」批判や、道頓堀の「中国化」現象は、訪日外国人観光客が日本の観光地にもたらす光と影の両面を浮き彫りにしています。経済的な恩恵をもたらす一方で、伝統的な街の雰囲気や地域住民の体験が変化し、時には摩擦を生むこともあります。これらの変化にどう向き合い、日本の魅力を保ちつつ多様な観光客を受け入れるか。これは、これからの日本の観光業が直面する重要な課題と言えるでしょう。
参考文献
- 日本経済新聞取材班著『ニッポン華僑100万人時代 新中国勢力の台頭で激変する社会』(KADOKAWA)
- ドコモ・インサイトマーケティング (携帯電話の位置情報に基づく訪日観光客動態調査)
- Yahoo!ニュース (掲載元記事)