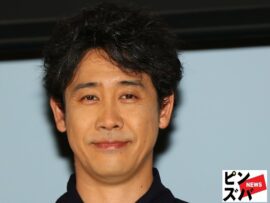自民党と公明党の長きにわたる「蜜月」が終焉を迎えようとしている。高市早苗氏が自民党新総裁に選出され、その直後の党人事を受けて公明党が連立離脱を表明したことで、日本の政治情勢は新たな局面を迎えている。社会学者の西田亮介氏は、公明党が自民党の「政治とカネ」の問題に耐えきれなくなったことが連立解消の大きな余波を生み、現行の自民党と他党が連立を組む価値は低いと指摘する。この動きは、日本の政界における大規模な再編や政権交代の可能性を示唆している。
 自公連立の将来を巡り議論する議員たちのイメージ:高市総裁選出後の政界の動き
自公連立の将来を巡り議論する議員たちのイメージ:高市総裁選出後の政界の動き
高市総裁選出が引き金に:公明党、連立離脱の背景
政権交代、そして政界再編が現実的な選択肢として急浮上する直接的な引き金となったのは、高市早苗氏が自民党の新総裁に選出されたこと、そしてその直後の自民党による新人事だった。公明党が連立離脱を表明した背景には、自民党が「政治とカネ」の問題を一向に解決しようとしない姿勢に対し、公明党と支持母体である創価学会が我慢の限界に達したという事情がある。公明党は強い危機意識を抱いており、近年、創価学会と公明党の間で主張の乖離が拡大してきたことも無関係ではない。創価学会は公称800万世帯を擁するものの、公明党員は45万人とされており、両者が常に一枚岩ではないことが示されている。学会内部の多様な政治的志向性から、付き合いで選挙運動を手伝っても、不満があれば投票しないというケースも少なくない。
創価学会と公明党の乖離:「一枚岩ではない」支持基盤
宗教団体である創価学会と比較して、公明党は過去25年以上にわたり自民党との連立政権を経験し、現実政治と日々向き合ってきた。その中で、公明党がより現実的な立場を取るのは当然と言える。筆者は2010年代半ばの平和安全法制を巡る議論あたりから、創価学会と公明党の主張の間に乖離が大きくなったと捉えているが、令和の「政治とカネ」の問題は公明党に決定的な負のインパクトを与えた。この問題は、公明党が将来を担うと目していた有力な中堅・若手議員の2024年総選挙や2025年参院選での落選を招き、議席数を減少させる結果となった。さらに2025年の東京都議選では、新宿区や大田区といった重要選挙区での落選も経験し、この状況に対する創価学会員や公明党の地方議員からの怒りの声は非常に強い。
「政治とカネ」が公明党に与えた深刻な影響
裏金問題の主な原因は自民党議員、特に旧安倍派に起因するものであり、公明党からすれば「もらい事故」のようなものであった。それにもかかわらず、公明党は選挙での苦戦を強いられ、支持基盤からの不信感を募らせていた。その上で、自民党の新総裁に高市氏が就任し、その後の党人事で公明党批判を繰り返してきた麻生派が重用され、さらに「政治とカネ」問題の渦中にあった人物が再登板したことで、公明党の我慢はついに限界を迎えたのである。これは単なる政党間の意見対立を超え、連立政権の根幹を揺るがす深刻な「政治不信」の問題として、公明党が連立の意義を見直す大きな要因となった。
結論:連立解消が導く政界の未来
自民党と公明党の連立解消は、単なる表面的な政変ではなく、長年にわたる政治の「ゆがみ」が表面化した結果である。高市早苗氏の自民党総裁選出とそれに続く人事が決定打となったが、根本原因は自民党の「政治とカネ」を巡る問題への不誠実な対応にあった。この状況は公明党、特にその支持母体である創価学会の内部で鬱積していた不満を爆発させ、複数の選挙での敗北がその怒りをさらに強めた。今後、日本の政界は予測不能な再編の時代へと突入する可能性があり、有権者の選択が日本の未来を大きく左右することになるだろう。
参考文献
- Yahoo!ニュース (President Online) – 自公連立の蜜月が終わり「高市早苗総理大臣」の誕生が危うくなっている…公明党が連立離脱を表明した本当の理由 (2025年10月17日)