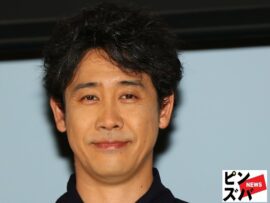第1回【コメ価格「5キロ4316円」で最高値を更新…「おこめ券」が解決につながらない根本的な理由 コメ農家が危機感をあらわにする「2文字」とは】からの続き──。農林水産省は11月14日、全国のスーパーで販売されたコメ5キロの平均価格が3日から9日の週で4316円に達し、過去最高を記録したと発表した。(全2回の第2回)
【写真】大木にクッキリ刻まれたクマの爪痕、綺麗に整えられていた棚田は荒れ放題に…農地が荒廃すると何が起きるのか
***
担当記者は「コメの価格が高止まりすれば、コメ農家にとっては収入増の可能性があります」と言う。
「収入増は農家にとって紛れもないメリットですが、高価格で消費者の“コメ離れ”を加速させるというデメリットもあります。実際、XなどのSNSでは『日本人の主食はパスタになってしまった』という投稿が非常に増えています。あまりにも高額でコメが買えず、パスタ、うどん、ラーメン、日本そばといった麺類にシフトしているのです。どうしてもコメが食べたいという家庭は外国産米を買っています。筆頭はカルフォルニア米で、台湾米も健闘しています」
一方、コメの価格が下がると消費量は増えるかもしれないが、農家の収入は減る。一体、どうすればいいのか──。
この切実な問いに、民放キー局の情報番組で「日本のコメ農家が大規模化すれば解決する」と主張するコメンテーターがいる。
大規模化すれば生産コストが下がる。生産増でコメ価格が下落しても、原価も下がっているから農家の被害は少ない。もし日本国内の消費量を上回る生産量に達すれば、余剰分は海外に輸出すればいい……。
木村和也氏は登山専門誌「山と溪谷」で知られる出版社・山と溪谷社のOBだ。生まれ育った新潟県南魚沼市にUターンすると実家のコメ農家を継ぎ、フリーペーパー「山歩みち」の編集長を務めている。
加速する離農
木村氏は「確かに大規模化は進んでいます。南魚沼市でも小規模の農家は離農が相次いでいるのに対し、5ヘクタール以上の耕地面積で営農する農家は3倍以上増えました」と言う。
「結果、南魚沼市の全農家数に対する大規模農家の比率は1%から5%に上昇しました。南魚沼市は平坦な耕地が少ない『中山間地域』ですが、それでも大規模化が進んでいます。となると平野が広がる地域では、さらに大規模化が進んでいると考えて間違いないでしょう。事実、一部の農機具メーカーは個人農家との取引を避けるようになっており、大規模農家に焦点を合わせた営業を始めています。こうなると、さらに個人農家の離農は加速していくと考えられます」
短期的には、コメの価格は上昇や下落を繰り返すかもしれない。だが長期的な視野に立てば立つほど、今のままでは国産米の価格は高止りする可能性が高いという。
なぜなら、国の無為無策で農家の数と耕地面積が減少するのは避けられず、コメの“絶対生産量”は今よりも減ってしまうからだ。