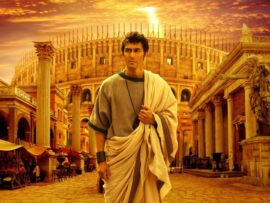自民党が高市早苗首相のリーダーシップのもと、26年間続いた公明党との協力関係を解消し、新たに日本維新の会との連立政権を樹立しました。この新たな政治の動きに対し、元衆議院議員の山尾志桜里氏は、両党が締結した12項目の「連立政権合意書」を詳細に読み解き、その中に潜む懸念を指摘しています。本稿では、山尾氏の分析に基づき、高市・維新連立政権の基盤と、その合意書に示された重要課題について深掘りします。特に、強固な共通基盤を持つ一方で、政治改革や憲法、皇室問題といった分野で曖昧さが残る点に焦点を当てていきます。
小泉政権を凌駕する高市・維新の「相性の良さ」
今回の高市内閣の実現において、日本維新の会はもう一方の主役でした。山尾氏は、仮に存在したであろう小泉政権よりも、実際には高市政権の方が維新との「相性が良かった」と分析しています。この親和性は、両者が「叩き上げのひたむきさ」という共通のバックボーンで強く結びついていることに起因すると推察されます。世襲や富豪ではないからこそ、自らの力で政策を磨き上げ、民意を勝ち取ってきた経験が共通しています。当初は人間関係が希薄であったかもしれませんが、政策協議を重ねるうちに、この共通の精神性が響き合い、互いに納得のいく協力関係の構築に至ったと考えられます。
合意文書の総論には、この相性の強さが色濃く反映されています。安全保障に関しては「リアリズム」に立つと明記されており、これは国際政治におけるパワーバランスという現実を見据えた安全保障観で合意し、「理想主義・夢想主義」的な立場を取らないことを明確に打ち出しています。経済においては、国民生活の向上は「経済成長」によってのみ達成されるとされており、「脱成長論」的な立場ではないことが示されています。安全保障と経済というこの二つの主要な軸で足場が共有できていることは、思いのほか強固な協力基盤となる可能性を秘めていると言えるでしょう。
 日本維新の会代表の吉村洋文氏と自民党総裁の高市早苗首相が、新連立政権について会談する様子
日本維新の会代表の吉村洋文氏と自民党総裁の高市早苗首相が、新連立政権について会談する様子
合意書に潜む課題:曖昧な政治改革と拙速な憲法・皇室論
しかしながら、この連立合意書の各論には、いくつかの懸念点が浮かび上がると山尾氏は指摘します。
まず一点目は、広く指摘されている政治改革の方向性の曖昧さです。特に企業団体献金については、「高市総裁の任期中に結論を得る」とありますが、具体的な期限や目指すべき方向性が示されていません。過去の「裏金問題」が依然として人材登用を事実上縛っている現状を鑑みると、これは率直にもったいないと言わざるを得ません。未来に向けた政治献金の構造改革を実行すれば、国民からの理解をさらに深めることができるでしょう。また、議員定数削減よりも企業団体献金規制の方が、国民の側を向いた政治の実現に直接的に寄与するはずであり、この点からも曖昧さは残念な要素です。
もう一点懸念されるのは、憲法と皇室に関する議論の運びの粗さです。今回、自民党と日本維新の会は、憲法改正(特に9条と緊急事態条項)に関して両党の協議会を設置すること、そして皇室のあり方については男系男子養子縁組案を優先することを合意しました。しかし、山尾氏は、これらの極めて重要なテーマにおいては、政権与党だけの枠組みに限定するよりも、超党派の枠組みをより重視すべきだと主張しています。具体的には、憲法に関しては、憲法審査会における超党派の条文起草委員会の発足を重視すべきであり、皇室に関しては、既に動いている立法府での超党派の協議体をさらに活性化させるべきであると提言しています。これらの提言は、国民的合意形成をより重要視する観点からのものです。
高市政権と日本維新の会の新たな連立は、安全保障と経済成長という強固な共通基盤を持つ一方で、政治改革の具体的な方向性や、憲法・皇室といった国家的根幹に関わる問題に対するアプローチには、依然として曖昧さや課題が残されています。これらの懸念に、新政権がどのように向き合い、国民からの信頼と理解を深めていくのかが、今後の重要な焦点となるでしょう。
参考文献
- Yahoo!ニュース – 吉村洋文代表、高市早苗首相(記事本文)
- 新潮社デイリー新潮掲載記事より山尾志桜里元衆院議員の分析に基づく