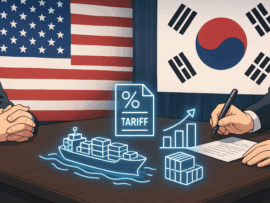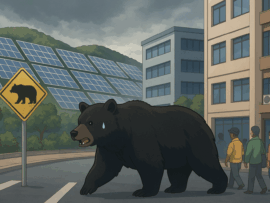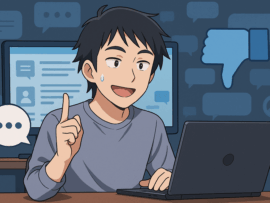[ad_1]
感染経路が不明な新型コロナウイルスによる肺炎患者の報告が相次ぎ、不安が高まっているが、感染しても健康な人ならば軽い症状で済む場合が多い。平成21年に国内で新型インフルエンザが流行した際には、医療機関に軽症者が殺到して混乱が起きた。これを教訓に、限られた医療資源を有効活用するには過剰に反応せず、「正しく恐れる」ことが重要だ。
17日に示された新型コロナウイルスに関する「相談・受診の目安」は、軽症者が医療機関に殺到して診療機能が損なわれるのを防ぎながら、重症者を早期に見つけて治療につなげる狙いがある。厚生労働省は感染拡大に備え、感染の疑いのある人を診療する専門外来を21年の新型インフル並みの800カ所に拡充するなど体制強化を図っている。
新型インフルの際にはウイルスが封じ込められず、感染が広がった。医療機関に「発熱外来」を設置したが、風邪による発熱など一般患者も押し寄せ、大阪府や兵庫県で発熱外来がパンクした。反省を踏まえ今回は、専門外来を原則非公開とし、全国536カ所ある相談センターから紹介する形をとる。
政府の専門家会議のメンバーを務める東京慈恵医大の吉田正樹教授(感染制御科)は「症状の軽い人は自宅でしばらく様子をみてほしい」と呼びかける。現状では医療機関を受診しても検査が難しい上、専用の治療薬もないためだ。外出により感染リスクも高まる。
長崎大の安田二朗教授(新興ウイルス感染症学)は「重症化しているのは高齢者や基礎疾患のある人。若い健康な人は軽症で済んでいる場合が多い。パニックになる必要はない」と指摘し、「感染を広げないという国民の認識を高めることが大事だ」と訴える。
今回のウイルスはせきやくしゃみ、鼻水や唾液の飛(ひ)沫(まつ)によって広がる。特に手にはウイルスが付着しやすい。国際医療福祉大の和田耕治教授(公衆衛生学)は「誰もが感染しうる状態にある。手洗いを軽く考える人がいるが徹底することが対策につながる」と語る。安田氏は「対策はここ数週間が正念場だ」と強調している。(長嶋雅子)
[ad_2]
Source link