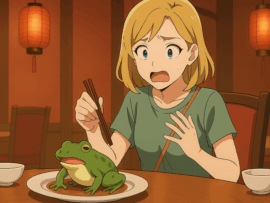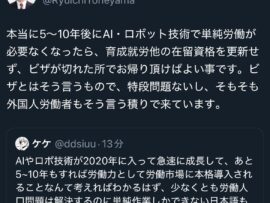[ad_1]
検察庁法をめぐる問題に、かねて疑問に思うことがあった。
今年1月、東京高検の黒川弘務検事長の定年延長が閣議決定された。検察庁法に定年延長の規定はなく、検察の歴史に勤務延長の前例もなかった。
森雅子法相は2月3日の衆院予算委員会で根拠を問われ「検察庁法は国家公務員法の特別法に当たり、特別法に書いていないことは一般法である国公法が適用される。検察庁法22条には定年年齢は書いてあるが、勤務延長の規定は記載されていないので、国公法が適用される」と答えた。
だが検察庁法22条には、こうあるだけだ。「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」
勤務延長の規定がないばかりか、定年の2文字もない。主語は検事総長、検察官であり、いずれも一定年齢に達した時に「退官する」のだ。素直に読めば、検察官は定められた年齢で自動的に自ら退官するのであり、他者に干渉の余地はない。その潔さは行政官であるとともに準司法官でもある検察官の自主と独立を象徴したはずだ。
法とは人や社会、職業などの規範を言葉としたものだろう。司法に携わる者は、ことさら言葉に忠実でなければならないはずだ。
大阪地検特捜部の証拠改竄(かいざん)事件を受けて最高検は平成23年、検察の再生に向けて「検察の理念」を制定した。
そこには、こうある。
「権限の行使に際し、いかなる誘因や圧力にも左右されないよう、どのような時にも、厳正公平、不偏不党を旨とすべきである。また、自己の名誉や評価を目的として行動することを潔しとせず、時としてこれが傷つくこともおそれない胆力が必要である」
「誘因や圧力」には、属人的な人事介入も含まれると解釈する。よもや地位に恋々としたとは思えず、そこにどんな事情があったのか、あずかり知らない。それでも、黒川氏は63歳の誕生日である2月8日を前に、検察庁法の規定に沿い、退官すべきだった。
検察庁法をめぐって国会が揺れた。改正案では極めてシンプルだった22条に7項が加えられ、かなりの長文となる。7項中、文頭の主語は2項は法務大臣、2項は内閣だった。
[ad_2]
Source link