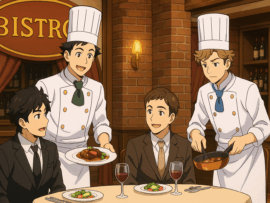[ad_1]
以前、当欄で昭和20年代の産経新聞の論調について書いた(平成30年11月25日)。趣旨は次のようなものだった。
産経は、産業経済新聞として戦後しばらくまで経済紙だったこと。各地で頻発した過激な労働争議を、復興を妨げるものとして再三、批判したこと。過激な争議の背後にある共産主義思想と早くから対決していること、などである。このような左派との戦いは終戦後の早い時期に始まっていた。
ロシア革命を指導したレーニンが国家を階級支配の機関とみなし、その死滅を訴えたように、左派は国家に対して否定的である。それと反対に、産経は国家の自立を早い段階から訴えた。そのことにも触れた。
昭和30年代について報告したい。20年代と同じく、私見であることをお断りしておく。引用は大阪本社版の紙面から。
◆「憲法は改正すべし」
結論を先にいうと、左派との戦いは30年代も貫かれている。労働争議だけでなく、特定の意図に導かれた政治デモなどへの批判となって展開される。
30年代は、長く政治の枠となった「55年体制」の成立とともに始まった。左右社会党が統一され、保守合同で自民党ができたのが30年(1955年)である。世界的に見れば共産主義国と自由主義国の対立が続いていた。それに対応するように日本でも保革が対立する。
保守合同の際、社説(現在の「主張」)は保守政党がなすべき課題を次のように述べた。
「日本の独立を真実のものとすることである。(略)自然に防衛は自力をもってすべく、その障害となる憲法は改正すべしということになる」(30年11月15日)
◆左翼を批判
統一された社会党は、独裁は否定したものの、そのイデオロギーは共産主義に近いものだった。当時、国会でしばしば実力行使に及んだ。社説は「恐らく共産党的労働組合の暴力革命手段としての闘争戦術を導入したものであろう」と分析した(31年5月22日)。
批判は、社会党の支持母体である労働組合組織、総評や、その構成団体である日教組にも向けられた。社説はそれらの「綱領や運動方針その他に現われた考え方が著しく共産主義的であることは今や常識である」としている(31年6月2日)。
30年代の特に前半は左派の暴風が吹き荒れた時代である。米軍基地や教員の勤務評定に対する反対運動が頻発した。社説はこうした動きの背後にある共産主義思想に警鐘を鳴らした。33年8月28日の社説は勤務評定闘争などを批判し、「共産主義者はもとより社会党から戦闘的な労働組合までを貫く大きな思想的底流の中には手段を選ばぬ全体主義的な考え方が強く根をはっている」と注意を促した。
社会全体が大きく左傾していたといってよい。自由主義陣営に立つ日本を揺さぶろうとする、共産国からの働きかけも直接、間接にあった。
国会の内外で繰り広げられた最大の騒動が35年の安保闘争である。35年1月3日の社説は日米安保条約が日本にとって利益であることを指摘し、「国際的に左翼勢力をあげて改定阻止にかかっているからこそ、その運動を成功させてはならない」とした。デモが激化して死者を出すに至ると、混乱を招いた政府与党の姿勢をただすとともに、「ともすれば暴走しようとする」国内の反米勢力を非難した(35年6月16日)。
◆進歩的文化人も
このように、産業経済新聞であるがゆえに始まった反共路線は30年代も続いている。
革新政党や組合だけが日本の左傾の旗を振ってきたのではない。多分に容共的な大学教授ら、いわゆる「進歩的文化人」も批判している。39年1月10日の朝刊1面コラムは、マルクスとエンゲルスの『共産党宣言』が書かれて100年以上たっているのに、「そのこっとう品をまだ生き仏だと思っているのが日本の『進歩的文化人』だ」と手厳しい。
筆者の理解では、20年代、30年代の日本で猛威を振るった左傾思潮はその後も完全には退潮していない。左派が掲げた憲法擁護の声は今に至るも根強く残る。あるいは、自国を否定的に見る歴史観として現れもする。
それにしても、35年7月10日の朝刊1面コラムが「親ソ反米でないと雑誌が売れない」と嘆く時代だった。自賛するのではないが、よく正論を述べ続けたものと思う。(かわむら なおや)
[ad_2]
Source link