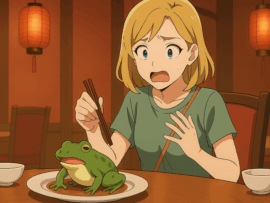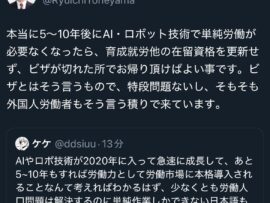かつて「海に浮かぶ軍艦」と称され、世界一の人口密度を誇った長崎県・端島(通称:軍艦島)。TBS日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』では、昭和の高度経済成長期におけるこの島の生活が鮮やかに描かれています。この記事では、ドラマを監修する黒沢永紀氏の解説を基に、当時の島民たちの過酷ながらも力強く生きていた様子、そして未来への希望を繋いだ海底水道プロジェクトについて掘り下げていきます。
水も貴重だった島での生活
ドラマ第2話では、台風による給水船の運航停止で海水での生活を強いられる島民の姿が描かれました。これはフィクションではなく、当時の現実でした。川や湧水といった水源を持たない端島では、水はまさに命の源。海底水道完成以前は、1日3回運搬船が真水を運び、1500トンのタンクに貯水していました。炭鉱長や職員には専用の配水係がいましたが、炭鉱員たちは水券と交換に給水栓から水を汲み、自宅まで運ぶ必要があったのです。貴重な水を水瓶に溜め、大切に少しずつ使っていたという当時の生活ぶりは想像を絶します。
 給水船から水を運ぶ様子を想像させる軍艦島の風景
給水船から水を運ぶ様子を想像させる軍艦島の風景
ドラマ第1話で描かれた炭鉱員の風呂も、一番湯と二番湯は海水、上がり湯のみ真水でした。黒沢氏によれば、「複数の浴槽で汚れを落とし、最後に真水で洗い流す。炭鉱員は怪我も多かったため、海水が傷にしみて痛かったのではないでしょうか」とのこと。風呂だけでなく、学校のプールも海水を使用。タンクの水が不足すると、洗濯の下洗いにも海水を使うなど、工夫を凝らした生活が送られていたのです。
希望を繋いだ海底水道プロジェクト
そんな不便な生活を改善するため、立ち上がったのが第3話で描かれた海底水道プロジェクトです。アメリカの原油パイプライン技術を参考に、端島と隣の高島を本土の野母崎の水源と繋ぐという壮大な計画。水深45メートル、全長11キロメートルにも及ぶ、世界でも類を見ない日本初の海底水道でした。完成後は各家庭に水道が設置され、蛇口をひねれば水が出るという、現代では当たり前の生活が実現しました。しかし、長年の水不足から解放された島民たちは、水の使いすぎに陥ってしまったといいます。当初の水源だけでは足りず、大きな貯水池が建設されるまでの約5年間は、皮肉にも節水生活が続いたというエピソードも残されています。
スカイツリーよりも深い坑内での過酷な労働
第2話で斎藤工さん演じる炭鉱員の進平が語っていたように、端島の炭鉱の坑道は非常に深く、東京スカイツリー(634メートル)を埋めても届かないほどでした。24時間3交代制で、地熱の影響で気温35℃、湿度80%超えという過酷な環境での作業。黒沢氏は、「炭鉱員にとって重要なのは、掘る体力よりも、この高温多湿な環境に慣れることでした。慣れないと脱水症状になり、すぐにバテてしまうこともあったでしょう」と解説しています。
危険と隣り合わせの炭鉱作業
落盤、坑内火災、ガス爆発など、炭鉱の作業は常に危険と隣り合わせでした。特に、最前線で石炭を採掘する採炭員や坑道を掘り進む掘進員は、粉塵を吸い込み、「珪肺」という病気を患うリスクがありました。第1話で咳き込んでいた鉄平の父・一平も、長年の炭鉱労働で肺を病み、週3日しか働けなくなっていました。
炭鉱の仕事は専門職で、担当が変わることはほとんどなかったそうです。坑外作業の方が珪肺のリスクは低いものの、最前線での作業を希望する炭鉱員が多かったといいます。「採炭は最も高給でしたが、それは命の危険を覚悟の上での仕事でした」と黒沢氏は語ります。ダイヤモンドと同じ炭素でできていることから「黒いダイヤモンド」と呼ばれた石炭。端島産の石炭は国内最高値で取引され、島民の豊かな生活を支えていました。
日本社会の縮図としての端島
黒沢氏は、筑豊炭鉱で働き、その様子を記録した山本作兵衛についても言及。山本作兵衛の自伝には「炭鉱は日本社会の縮図」という言葉が残されています。全国から様々な事情を抱えた人々が集まり、まるで一つの国家のような共同体で暮らしていた端島。黒沢氏は、「現代日本を築き上げた、国家の縮図のような島だった」と、その歴史に思いを馳せています。
現代の私たちにとって想像もつかない過酷な環境の中、希望を胸に懸命に生きていた人々の物語。ドラマ『海に眠るダイヤモンド』を通して、当時の生活に想像を巡らせ、今の私たちの生活の礎を築いた先人たちの努力に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。