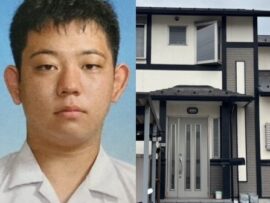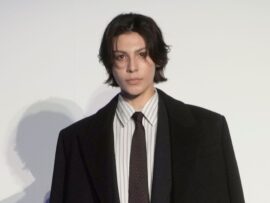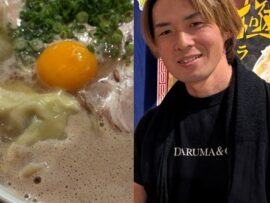少子化が加速する一方で、深刻な社会問題として浮き彫りになっているのが、子どもの不登校です。文部科学省の調査によると、令和5年度の不登校児童生徒数は過去最多の34万6482人を記録し、11年連続で増加しています。一体なぜ、これほどまで不登校が増え続けているのでしょうか?
制度疲労を起こした学校教育システム
長年、不登校やひきこもりの支援に携わってきた精神科医の斎藤環氏(筑波大学名誉教授)は、この現状を「異常事態」と警鐘を鳴らしています。斎藤氏によると、不登校増加の根本原因は、学校教育システムの制度疲労にあるといいます。
 不登校のグラフ
不登校のグラフ
社会は常に変化しているにもかかわらず、学校の指導方針は昭和時代の少年非行予防対策モデルから脱却できず、時代に合わなくなってきていると斎藤氏は指摘します。少年の犯罪検挙件数は減少傾向にあるにもかかわらず、「問題行動を起こさせない」という指導方針が依然として優先されている現状に疑問を呈しています。
時代遅れの校則と息苦しい中学校生活
家庭の教育環境の変化なども不登校増加の要因として挙げられることもありますが、斎藤氏は社会全体の変化に比べればその影響は軽微だと考えています。特に問題視しているのが中学校です。小学6年生から中学1年生にかけて不登校児童生徒数が激増するデータからも、中学校生活の困難さが浮き彫りになっています。
「問題を起こさせない」指導の典型例として挙げられるのが、無意味な校則です。さらに、部活動の強制参加や年功序列といった旧態依然としたシステムも、生徒たちに息苦しさやストレスを与えている要因となっています。
理想的にはクラス制の撤廃が望ましいものの、生徒管理の効率性という観点から、今後もクラス制がなくなることはないだろうと斎藤氏は予測しています。
中学校は学習だけでなく、対人スキルや人格形成、スポーツの機会などを提供する場でもあります。不登校になると、これらの貴重な機会をすべて失ってしまう可能性があります。
魅力的な学びの場への転換を
斎藤氏は、韓国や中国といった競争的な教育環境と比較すればまだマシという相対的な見方もあるものの、学校が子どもたちにとってより魅力的な空間へと転換していくことの重要性を訴えています。
子どもたちのSOSを聞き逃さないために
不登校は子どもたちからのSOSのサインです。時代遅れの指導方針や息苦しい学校環境を見直し、子どもたちが安心して学び、成長できる環境を整備することが急務となっています。