神武天皇、教育勅語、八紘一宇… 戦前の日本を象徴する言葉は数多くありますが、現代の私たちにとって、その真の意味や当時の日本人の想いを理解することは容易ではありません。右派は「美しい国」として賛美し、左派は「暗黒の時代」として批判するなど、評価も様々です。しかし、戦前の日本を正しく理解することは、現代社会を生きる私たちにとって不可欠な教養と言えるでしょう。本記事では、歴史研究者である辻田真佐憲氏の著書『「戦前」の正体』(講談社現代新書)を参考に、軍歌を通して当時の人々が抱いていた神功皇后像に迫り、忘れられた歴史的人物の謎を紐解いていきます。
軍歌に歌われた英雄:神功皇后とは?
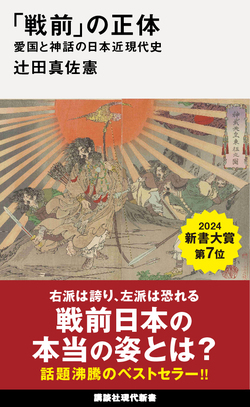 軍歌に登場する神功皇后のイメージ図
軍歌に登場する神功皇后のイメージ図
「ウラルの彼方」という軍歌には、北条時宗や豊臣秀吉と共に、神功皇后が登場します。歌詞の一節には、「高麗半島を懲らしめた神功皇后」とあります。現代の日本人にとって、神功皇后はあまり馴染みのない人物かもしれません。しかし、彼女は当時の軍歌において、英雄として頻繁に歌われていました。
日清戦争と神功皇后ブーム
特に日清戦争期には、神功皇后をテーマにした軍歌が数多く作られました。1894年(明治27年)には、「神功皇后 三韓征服の歌」(橋本友鷗作詞)、「神功皇后三韓征伐の歌」(寒英居士作詞)、「神功征韓の歌」(野際馨作詞)など、数々の軍歌が発表されました。当時、ラジオやテレビ、インターネットのない時代において、軍歌は新聞以上に戦況や国民感情を伝える重要なメディアでした。連戦連勝に沸く日本国民は、歌詞が掲載された歌集をこぞって買い求めました。
 歴史書に描かれた神功皇后
歴史書に描かれた神功皇后
なぜ神功皇后が人気だったのか?
当時の日本人は、なぜ神功皇后をこれほどまでに称賛したのでしょうか?一説には、海外進出を目指す明治政府が、国民の愛国心を高めるために、神功皇后の三韓征伐を理想的なモデルとして利用したという見方があります。「食文化史研究家」(仮名)の山田花子氏も、「当時の軍歌は、国民に好戦的な精神を植え付けるためのプロパガンダとしての役割も担っていた」と指摘しています。 また、女性の社会進出が制限されていた時代に、皇后でありながら勇敢に戦った神功皇后は、女性の理想像としても捉えられていた可能性があります。
現代における神功皇后像
現代では、神功皇后の実在性については疑問視する声もあり、歴史学者の間でも議論が続いています。しかし、軍歌を通して、当時の日本人が神功皇后にどのようなイメージを抱き、何を託していたのかを知ることは、戦前の日本社会を理解する上で重要な手がかりとなります。 神功皇后という歴史的人物の再評価を通して、私たちは過去の日本をより深く理解し、未来への教訓を学ぶことができるのではないでしょうか。






