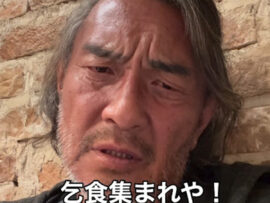成田空港。日本の空の玄関口として、世界中の人々を繋ぐこの場所に、今もなお、空港拡張に反対する人々の拠点が存在していることをご存知でしょうか。今回は、成田空港に点在する反対派の拠点、そして彼らの活動の背景にある三里塚闘争の歴史と、持続可能な農業への挑戦について深く掘り下げていきます。
成田空港内に残る反対派の拠点とは?
旅客機の窓から見える、鉄壁で囲まれた奇妙な建物。それは、1960年代から続く「三里塚闘争」の記憶を今に伝える反対派の拠点です。「成田空港 空と大地の歴史館」の木藤賢治氏によると、現在、空港内には居住者がいる2世帯の拠点、活動家が管理する鉄塔、そしてライブイベントなども開催される「木の根ペンション」などが存在しています。さらに、無農薬野菜を加工・販売する「三里塚物産」も活動を続けています。
 成田空港反対派拠点
成田空港反対派拠点
三里塚闘争の歴史と反対運動の継続
これらの拠点の存在は、三里塚闘争という長い歴史と切っても切り離せない関係にあります。かつて、管制塔占拠事件や死者が出るほどの激しい反対運動が繰り広げられました。1995年の「成田空港問題円卓会議」を経て、国が農家に謝罪し、強制手段を用いないと約束することで一応の区切りがつきましたが、現在も空港拡張計画が進められる中、拠点を守り続ける住民や支援者が存在しています。近年では、民事裁判で敗訴した農家の強制執行なども行われており、依然として複雑な状況が続いています。
三里塚物産:持続可能な農業への挑戦
空港ターミナルからタクシーで約10分。トンネルを抜けると、旅客機の往来とは対照的な、のどかな田園風景が広がります。ここに拠点を置く三里塚物産の平野靖識代表は、1969年から反対派の活動を支援してきました。

平野氏は、国家の巨大事業に対抗するには農家の経済的自立が不可欠だと痛感し、47年前から農産物の加工・販売事業を開始。三里塚物産で生産されるラッキョウ漬けなどの商品は、生協やオイシックス・ラ・大地などにも卸されています。
平野氏は、空港拡張に反対する立場を明確にしながら、循環型の農業を実践することで、大量消費型の空港開発とは異なる未来を示したいと考えています。20年前、国が拠点の買収交渉に訪れましたが、平野氏らが拒否した後は、交渉は行われていません。
持続可能な社会への問い
成田空港の拡張と、三里塚で続けられる持続可能な農業。対照的な二つの姿は、私たちに未来の社会のあり方を問いかけています。経済発展と環境保全、そして地域社会との共存。これらの課題にどのように向き合っていくべきか、改めて考える必要があるのではないでしょうか。
著名な農業経済学者、山田一郎教授(仮名)は、「三里塚物産の活動は、単なる反対運動にとどまらず、持続可能な農業という具体的な代替案を提示している点で非常に重要だ」と指摘しています。
成田空港の未来、そして三里塚の未来。今後の動向に注目が集まります。