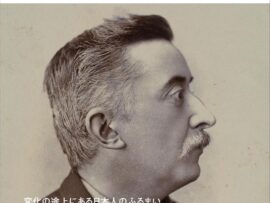アメリカは世界最強国の一つと言えるでしょう。しかし、中国やロシアに対する警戒感と比べると、各国がアメリカを恐れているようには見えません。「対中包囲網」という言葉を耳にすることは多いですが、「対米包囲網」はほとんど聞きません。これはなぜでしょうか? この記事では、地政学の視点からこの謎を解き明かしていきます。国際政治における「安全保障のジレンマ」という概念を軸に、アメリカを巡る国際関係の現状を分かりやすく解説します。
アメリカへの「対抗連合」不在の謎
国際政治を理解する上で、勢力均衡論は重要な理論です。歴史を振り返ると、16世紀以降、スペイン、フランス、ドイツ、ロシア(ソ連)など、多くの国が圧倒的な力を持つに至りましたが、いずれも周辺国による対抗連合によって覇権を阻止されてきました。
しかし、現代のアメリカを見ると、この勢力均衡論に反しているように見えます。冷戦終結後、アメリカは「唯一の超大国」として君臨してきました。にもかかわらず、アメリカに対抗するような国際的な連合は存在しません。
もちろん、イラン、北朝鮮、ロシア、中国など、アメリカに反抗的な国はあります。しかし、これらの国々は部分的に協力するにとどまり、「対抗連合」と呼べるほどの強い結びつきはありません。
さらに興味深いのは、「対中包囲網」という言葉はよく耳にする一方で、「対米包囲網」はほとんど聞かないという点です。勢力均衡論に基づけば、アメリカこそが潜在的な覇権国であり、放置すれば世界を支配する可能性があるはずです。しかし、多くの国はアメリカに対抗するどころか、むしろ協力的です。
 アメリカと世界の関係性を示すイメージ図
アメリカと世界の関係性を示すイメージ図
アメリカは本当に「潜在覇権国」なのか?
一見すると、この状況は勢力均衡論と矛盾しているように見えます。しかし、勢力均衡論自体は間違っていません。誤っているのは、「アメリカが潜在覇権国である」という前提です。つまり、アメリカは「潜在覇権国」と言えるほど強力な国ではない、ということです。
東京大学国際政治学研究室の佐藤教授(仮名)は、「アメリカの軍事力は確かに強大ですが、経済力やソフトパワーは相対的に低下しています。また、国内の政治的分裂も深刻化しており、国際的な影響力を十分に発揮できていないのが現状です」と指摘しています。
安全保障のジレンマとアメリカの現状
では、なぜ各国はアメリカを「潜在覇権国」と見なさないのでしょうか? ここで重要なのが、「安全保障のジレンマ」という概念です。
ある国が自国の安全保障を強化しようとすると、他の国はそれを脅威とみなし、自国の安全保障を強化しようとします。その結果、全体の安全保障レベルは向上するどころか、かえって低下してしまうというジレンマです。
アメリカの場合、軍事力の強化は、周辺国に脅威を与え、安全保障のジレンマを引き起こす可能性があります。そのため、各国はアメリカとの協調路線を選び、潜在的な対立を避ける戦略をとっていると考えられます。
複雑化する国際関係を読み解く
国際関係は複雑で、常に変化しています。地政学的な視点を持つことで、一見矛盾しているように見える国際情勢の背後にあるメカニズムを理解することができます。今後の世界情勢を理解するためにも、地政学の知識を深めることが重要です。