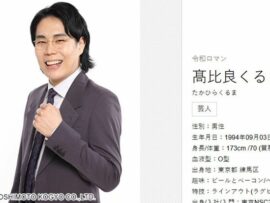人生の終焉は誰しもが避けては通れない道です。しかし、その「死に方」について真剣に考える機会は意外と少ないのではないでしょうか。この記事では、医師であり作家の久坂部羊氏の著書『死が怖い人へ』を参考に、後悔しない最期を迎えるための心構えを探っていきます。 どうすれば「上手な死に方」ができるのか、具体的なヒントと共にお伝えします。
「良い死に方」「悪い死に方」とは?
多くの患者の死を看取ってきた医師、久坂部羊氏は、「良い死に方」と「悪い死に方」があると指摘します。その違いはどこにあるのでしょうか? 鍵となるのは「死を受け入れる」という心構えです。
死を受け入れることの重要性
医療技術が進歩した現代でも、死を完全に避けることはできません。 しかし、多くの人は「死」をタブー視し、向き合うことを避けてしまいがちです。 久坂部氏によれば、死を拒絶し続けることは「間違った道へのスタートライン」に立つことと同じです。
 alt
alt
死は誰にでも訪れる自然な現象であると受け入れることで、残された時間をより有意義に過ごすことができるようになります。 死を恐れるのではなく、どうすれば悔いなく人生の幕を閉じることができるのか、前向きに考えることが大切です。
在宅医療から学ぶ「良い死に方」
久坂部氏は、病院での死よりも在宅医療で迎える死の方が「好ましい死に方」であると述べています。 なぜ在宅医療が「良い死に方」につながるのでしょうか?
家族との時間、そして自分らしい最期
在宅医療では、住み慣れた環境で家族に囲まれながら最期を迎えることができます。 病院という非日常的な空間ではなく、穏やかな雰囲気の中で大切な人々と過ごす時間は、患者にとって大きな心の支えとなります。 また、自分らしい生活を続けながら最期を迎えることができるのも在宅医療のメリットです。
残り時間をどう使うか?
「死」を意識することで、残された時間をどう使うべきかが見えてきます。 久坂部氏は、小説『悪医』の中で、テーマパークの閉園時間という比喩を用いて、残り時間をどう過ごすかという問いを投げかけています。
限られた時間を最大限に活かす
閉園時間が迫っている状況で、時間を延ばしてほしいと泣き続けるよりも、残された時間を最大限に楽しんで遊ぶ方が有意義です。 人生も同じです。死は避けられないからこそ、残された時間をどのように過ごすかが重要になります。 趣味に没頭する、家族との時間を大切にする、やり残したことに挑戦するなど、自分にとって大切なことを優先して時間を使いましょう。
専門家の意見: 「死の準備教育」の必要性
終活アドバイザーの山田花子さん(仮名)は、「死の準備教育」の重要性を説いています。「人生の最終章をどう締めくくるか、事前に考えておくことで、不安を軽減し、より穏やかな気持ちで最期を迎えることができる」と山田さんは強調します。
まとめ
「死に方」について考えることは、人生をより豊かに生きるためのヒントを与えてくれます。 死を受け入れ、残された時間を大切に過ごすことで、後悔のない人生を送ることができるでしょう。 この記事が、読者の皆様にとって「より良く生きる」ための一助となれば幸いです。