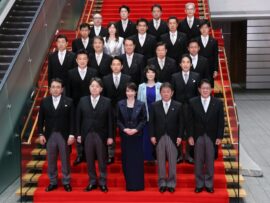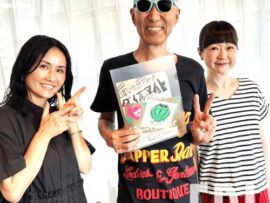現代社会において、ハラスメントの種類は増加の一途を辿っています。その中でも、近年注目を集めているのが「音ハラ(ノイズハラスメント)」です。音ハラは、日々の生活、特に職場環境において、深刻なストレスの原因となる可能性があります。この記事では、職場における音ハラの現状、具体的な事例、そして対策について詳しく解説します。
音ハラの実態:キーボードの音から、意外な音まで
職場における音ハラで代表的なのは、キーボードのタイピング音やマウスのクリック音です。これらの音は、静かなオフィス環境では想像以上に響き渡り、周囲の集中力を妨げる可能性があります。
 alt
alt
さらに、引き出しを開ける音、お菓子を食べる音、ペンをカチカチ鳴らす音など、一見些細に思える音も、音ハラに該当する場合があります。音の種類は実に多岐にわたり、人によって気になる音も異なるため、問題の複雑さを増しています。
音ハラ対策:企業と個人の取り組み
音ハラ問題への意識が高まるにつれ、企業側も対策に乗り出しています。静音キーボードや静音マウスの支給は、効果的な対策の一つと言えるでしょう。また、オフィスレイアウトの工夫や防音対策なども検討されています。
個人ができる対策とは?
個人レベルでも、音に配慮した行動を心がけることが重要です。例えば、キーボードやマウスを操作する際は、必要以上に力を入れず、静かに操作するよう意識しましょう。また、周囲の音に敏感な人がいる場合は、ヘッドホンやイヤホンを使用するなど、お互いに配慮し合うことが大切です。
職場の音ハラ体験談:髪の毛を触る音
都内のWeb広告会社で働く20代の女性Aさんは、同僚の男性Bさんのあるクセに悩まされていました。Bさんは、無意識のうちに髪の毛を触り、ジョリジョリとこする癖があったのです。
「静かなオフィスの中で、その『ジョリジョリ…』という音が、私だけに聞こえてくるんです。最初は我慢していましたが、次第に集中力が途切れ、仕事に支障が出るようになりました。」(Aさん)
Aさんは勇気を出してBさんに注意したところ、Bさんは自分の癖に気づき謝罪しました。しかし、無意識の癖はなかなか治らず、Aさんは今でも悩まされています。
音ハラで悩む前に:専門家の意見
職場の人間関係に詳しいコンサルタント、田中一郎氏(仮名)は次のように述べています。「音ハラは、加害者が悪意を持って行っているとは限りません。無意識のうちに周囲に迷惑をかけているケースも多いです。そのため、まずは相手に気づいてもらうことが重要です。」
田中氏は、音に悩まされている場合は、我慢せずに相手に伝えること、そして伝え方にも配慮することが大切だと強調しています。具体的には、「〇〇の音で集中できないので、少し控えてもらえると助かります」といったように、具体的な音と、自分がどう感じているかを伝えることが効果的だと言います。
音ハラの課題と未来:より良い職場環境を目指して
音ハラ問題は、個人の感受性や職場環境など、様々な要因が複雑に絡み合っているため、一概に解決策を示すことは難しいです。しかし、企業と個人が協力し、お互いに配慮することで、より快適な職場環境を実現できるはずです。
この記事が、音ハラ問題について考えるきっかけとなり、職場環境の改善に繋がることを願っています。