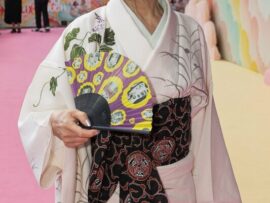日本における死刑制度が、大きな転換期を迎えています。長らく国民の支持を背景に維持されてきた死刑ですが、袴田事件の再審無罪確定や国際社会からの批判の高まりを受け、その存続が改めて問われています。
袴田事件再審無罪が突き付けた死刑制度の課題
 袴田巌さんと静岡地検検事正
袴田巌さんと静岡地検検事正
2024年10月、袴田巌さんの再審無罪が確定しました。48年もの歳月を獄中で過ごした袴田さんの無罪判決は、日本の司法制度、そして死刑制度のあり方に大きな衝撃を与えました。この判決は、冤罪の可能性を改めて浮き彫りにし、死刑制度の根幹を揺るがすものとなったのです。 死刑は一度執行されてしまうと取り返しがつきません。袴田事件のようなケースを二度と繰り返さないために、死刑制度の是非について、国民一人ひとりが真剣に考える必要があると言えるでしょう。
国際社会からの厳しい視線と日本の対応
2022年7月の死刑執行を最後に、日本では2年以上死刑執行が行われていません。この異例の事態の背景には、袴田事件の影響に加え、国際社会からの厳しい視線があります。国連特別報告者は、日本の死刑制度における「密行主義」、つまり執行の直前まで本人に告知せず、家族への連絡も事後という現状を「非人道的」と指摘。絞首刑という執行方法についても国際法違反の可能性を問うなど、日本の死刑制度に対する懸念を表明しています。
著名な人権弁護士である佐藤一郎氏(仮名)は、「国際社会の目は、日本が人権をどのように尊重しているかを注視している。死刑制度の運用方法を透明化し、国際基準に沿ったものに見直す必要がある」と述べています。

日本政府はこれまで、国内世論の支持を根拠に死刑制度を維持してきました。しかし、国際社会からの圧力が高まる中、従来の姿勢を維持することが難しくなってきているのも事実です。 今後、日本は国際社会との調和を図りながら、死刑制度のあり方をどのように見直していくのか、その選択が注目されています。
死刑制度の未来:国民的議論の必要性
袴田事件と国際社会からの批判は、日本の死刑制度の未来を大きく左右する重要な転換点となっています。死刑制度の是非、そしてその運用方法について、国民的な議論を深めていくことが必要不可欠です。