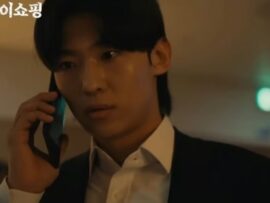2024年度の公立小中学校の年間授業計画において、標準時間数を大幅に超過している学校が依然として多いことが文部科学省の調査で明らかになりました。子供たちの学びを深めるための授業時間数確保と、教員や子供たちへの負担軽減の両立は、日本の教育現場における大きな課題となっています。
標準時間数を超過する学校の実態
文部科学省の調査によると、小学5年生(1コマ45分)では17.7%、中学2年生(1コマ50分)では15.2%の学校が、標準時間数である1015コマを大きく上回る1086コマ以上の授業を実施していることが分かりました。これは、22年度と比較すると小中学校ともに20ポイントほど減少したものの、依然として高い水準です。
 alt
alt
週31コマを超える授業時間数は、子供たちの学習負担を増大させるだけでなく、教員の疲弊にも繋がります。文部科学省は、本当に必要な時間数なのか、精査するよう求めています。
カリキュラム・オーバーロードの懸念
学習指導要領では年間35週以上の授業実施を規定しており、年間1086コマは35週換算で週31コマを超える計算になります。平日のみで消化しようとすると、1日に7コマ以上の授業を行う日が出てきてしまい、児童生徒にとって大きな負担となります。
教育関係者からは、学習指導要領で定められた学習内容が多すぎる「カリキュラム・オーバーロード」が背景にあるとの指摘が出ています。これは次期学習指導要領の改定作業における重要な論点となるでしょう。
授業時間数の現状と課題
今回の調査は全ての公立小中学校を対象に行われました。小学5年生の年間授業時間数の平均は1059.1コマ(22年度比19.2コマ減)、中学2年生は1058.4コマ(同15.5コマ減)でした。
過剰な授業時間数は、子供たちの学習意欲の低下や、ゆとりある学校生活の阻害に繋がることが懸念されます。一方で、質の高い教育を実現するためには、必要な学習内容をしっかりと確保することも重要です。
効率的な授業運営と質の向上に向けて
子供たちの学力向上と健やかな成長を両立させるためには、授業時間数だけでなく、授業内容の質の向上や、教員の負担軽減に向けた取り組みも不可欠です。ICTの活用や、地域社会との連携など、様々な工夫を凝らすことで、より効果的で効率的な教育の実現を目指していく必要があるでしょう。
未来の教育を見据えて
今回の調査結果は、日本の教育現場が抱える課題を改めて浮き彫りにしました。子供たちの未来のために、より良い教育環境を整備していくことが求められています。