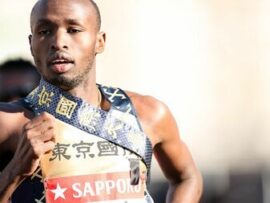大船渡市を襲った未曾有の山林火災。燃え広がる炎は、住民たちの生活を脅かし、未来への希望に影を落としています。この記事では、被害の現状と避難生活を送る住民たちの声、そして懸命な消火活動の様子をお伝えします。
延焼続く大船渡の山林火災、2002年以降最悪の規模に
岩手県大船渡市で発生した山林火災は、2月28日から延焼を続け、3月1日朝には焼損面積が約1400ヘクタールにまで拡大しました。これは、2002年以降、国内で発生した山林火災としては最悪の規模となります。三陸町越喜来の3地区にも新たに避難指示が出され、市内の11箇所の避難所には1033人もの住民が避難を余儀なくされています。
 大船渡中学校の避難所のグラウンドから見える山火事の様子
大船渡中学校の避難所のグラウンドから見える山火事の様子
避難生活の長期化に不安募らせる住民たち
避難所となっている越喜来小学校に避難してきた70代の女性は、火災現場近くの綾里地区から2月26日に上甫嶺地区の親戚宅へ避難していましたが、1日朝にはそこにも避難指示が出され、再び避難を強いられました。「数日で帰宅できると思っていたので、何も持たずに出てきた」と不安を口にしました。
また、大船渡高校の卒業式を控えた佐藤汐華さんは、避難所の駐車場で前髪を整えながら、「卒業式の後、友達とプリクラを撮る予定だったけど、できるかわからない。でも、もっと大変な人もいるから…」と、複雑な心境を明かしました。
甫嶺地区でダイビングショップ「みちのくダイビングリアス」を経営する佐藤寛志さんは、「震災の経験があるので、避難は迅速に行われています。今は避難に専念します」と力強く語りました。

震災からの復興途中に再びの試練
大船渡中学校の避難所には、東日本大震災で被災し、高台の大洞地区に転居してきた70代の男性の姿がありました。「津波の心配がない場所に引っ越してきて『もう大丈夫』と思っていたのに、今度は火事。家は大丈夫だと思うが、落ち着かない」と、繰り返される災害への不安を吐露しました。
ペットの猫と一緒に避難してきた40代の女性は、「猫だけ残すわけにはいかない。車と避難所を行き来して過ごします」と話しました。この女性は、家族で買い物中にスマホの緊急情報で避難指示を知り、すぐに自宅に戻って避難してきたとのこと。震災後に移転した高台にある自宅が再び危険にさらされ、「高いところにきたら次は火事。明日は子供の高校の卒業式なのに…」と、肩を落としました。
消防団員も懸命の消火活動、しかし情報不足と混乱も
大船渡市消防団の副団長を務める佐々木正人さんは、「確かな情報が乏しいまま、自宅に戻れない状況で、住民たちは疑心暗鬼になり混乱している」と現状を説明しました。佐々木さん自身も自宅の安否が分からず不安を抱えているといいます。
消防団は、2月19日に発生した最初の山林火災から休むことなく活動を続けてきました。一度は鎮火したと思われた矢先に再び発生した今回の火災。強風のため消防団は退避を余儀なくされ、少なくとも84軒が焼失したと発表されていますが、現場に入って詳細を確認できない状況が続いています。「なぜ火災が起きたのか、気持ちが整理できない」と佐々木さんは無念さをにじませました。
専門家の声:山林火災の予防と対策
山林火災の専門家である(架空の専門家)山田教授は、「今回の火災は、乾燥した天候と強風が重なったことが大きな要因と考えられる。山林火災を防ぐためには、火の元の管理を徹底することはもちろん、地域住民が協力して防火帯の整備や早期発見体制の構築に取り組むことが重要だ」と指摘しています。
大船渡市の山林火災は、今もなお燃え広がり続けています。一日も早い鎮火と、被災された方々の生活再建を心から願います。
この他にも、山梨県大月市や長野県上田市でも山林火災が発生しており、全国的に乾燥した天候が続く中、火災への警戒が必要です。