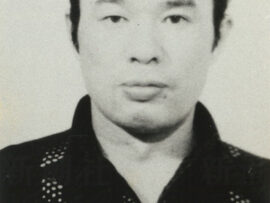江戸時代を舞台にした池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』で有名な火付盗賊改方長官、長谷川平蔵。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、その若き日の姿が描かれ、話題を呼んでいます。豪快で粋な江戸っ子として知られる平蔵ですが、実は若い頃は放蕩息子だったという一面も。この記事では、ドラマを通して明らかになった平蔵の意外な一面と、彼の父・宣雄の活躍に迫ります。
若き日の平蔵:豪遊と「本所の銕」の異名
ドラマ「べらぼう」では、中村隼人さん演じる若き日の平蔵が登場します。吉原遊郭で散財する旗本のお坊ちゃまとして描かれ、どこか憎めないキャラクターとして視聴者の心を掴んでいます。実はこの描写、史実にも基づいているのです。平蔵は若い頃、放蕩無頼の生活を送っていたと言われており、「本所の銕(てつ)」という異名で知られていました。この異名は、幼名である銕三郎と、当時本所に住んでいたことに由来しています。後に家督を継いだ後も、父の遺産を遊郭で使い果たしたという逸話が残っています。
 alt明和の大火を描いた絵巻物。長谷川平蔵の父、宣雄は、この大火の真相究明に尽力しました。
alt明和の大火を描いた絵巻物。長谷川平蔵の父、宣雄は、この大火の真相究明に尽力しました。
父・宣雄:明和の大火と誠実な捜査
平蔵の父、長谷川宣雄もまた火付盗賊改方として活躍した人物です。明和8年(1771年)に発生した「明和の大火」では、約1万4000人もの死者が出るという未曾有の大惨事となりました。宣雄は、この火災が放火であると睨み、徹底的な捜査を開始。ついに犯人を捕らえ、自白を引き出すことに成功します。
当時の火盗改は、拷問によって自白を強要するケースも少なくありませんでした。しかし、宣雄は違いました。犯人の自白だけでは納得せず、現場検証や関係者への聞き取りを綿密に行い、事件の真相究明に全力を尽くしたのです。
宣雄の誠実な人柄が表れているのは、老中・松平武元への報告の際です。宣雄は、自らの取り調べだけでは判断できないとして、町奉行へ事件を引き渡したいと申し出ています。しかし、武元の判断により、最終的に犯人は火炙りの刑に処せられました。
現代社会においても、冤罪事件は後を絶ちません。長谷川宣雄の誠実な捜査姿勢は、現代の警察関係者も見習うべき点と言えるでしょう。
親子二代:火盗改の歴史に名を刻む
長谷川平蔵宣以とその父・宣雄は、共に火付盗賊改方として江戸の治安維持に貢献した人物です。若き日の放蕩ぶりから、後に「鬼平」として名を馳せることになる宣以。そして、誠実な捜査で「明和の大火」の真相究明に尽力した宣雄。二人の活躍は、江戸時代の火盗改の歴史に深く刻まれています。
大河ドラマ「べらぼう」を通して、長谷川平蔵の新たな一面に触れ、江戸時代の歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。