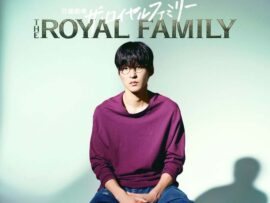およそ600年ものあいだ「世界史の中心」に君臨していたオスマン帝国。多民族・多宗教の大帝国は、いかに栄え、そして滅びたのでしょうか。
【写真】オスマン帝国「最強の軍事力」を支えた「異教徒の少年奴隷」軍団の正体
3月21日発売の『オスマン帝国全史』(講談社現代新書)著者・宮下遼さんが、今なぜオスマン帝国の歴史を学ぶ意味があるのかを解説します。
時は14世紀。「神に似たる御方」と讃えられたオスマン帝国の第3代君主・ムラト1世。彼がオスマン帝国を盤石にするべく行ったこととは?
歩兵部隊イェニチェリの創設
渡海に至適の海峡を抑えたとはいえ、アナトリアに比較すれば人口密度が高く、しかも数多くの要塞を擁するバルカン半島への進出には、従来のような騎兵主体の軍のみでは心許なかった。そのためムラト1世はすぐに城攻めや拠点防衛、そして船舶の運用に充てる歩兵部隊の大幅な拡充を行った。それがイェニチェリ部隊である。
17世紀に記された『イェニチェリの諸規則』という書物は、馬を運搬する船を操るための歩兵と海兵が、ダーダネルス海峡西岸のゲリボルにおいて募集されたのが軍団のはじまりであったとする。ところが、当初の募兵では到底足りず、ムラト1世はより組織的に兵士の徴発をはじめたという。それがキリスト教徒の村や街から定まった戸数ごとに1人ずつ少年を徴用し、これを養育して君主に直属の兵士や文官へと育てる徴発制度(デヴシルメ)である。
異教徒の少年を奴隷と成して教育するという一見、奇異な制度はとくに西欧のキリスト教徒たちによってオスマン帝国の特徴の1つとして長らく語り継がれたが、実のところ奴隷を教育して君主に忠誠を誓う戦士団を組織する伝統は──まさにトルコ人たちが奴隷騎兵としてイスラーム世界へ入来したように──アッバース朝の時代からイスラーム世界の各地で行われてきた。
またすでに、始祖オスマンの時代にも略奪遠征で獲得した捕虜のうち君主に献上される取り分から歩兵を育成する試みが細々と行われていたようなので、ムラト1世が実施した「徴発」は、決して前触れなく現れた制度ではなかった。さらに言えば、この制度が奴隷の徴発・養育・運用を一体化させて精緻に運用されるようになるのは15世紀を待たねばならない。
しかしいずれにせよ、この200年後には小銃を装備する銃兵隊へと様変わりしながら砲兵や輜重(しちょう)部隊、伝令部隊を従え、ルネサンス期地中海世界において空前の規模の常備軍となって長らくオスマン帝国の軍事力の象徴となるであろうイェニチェリ軍団は、当初は渡海聖戦のための補助役として歴史に姿を現したのである。