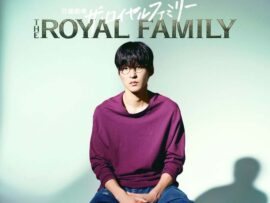自民党と日本維新の会による歴史的な連立政権が樹立され、高市早苗氏が新たな首相としてその舵を取ることになりました。この新体制発足の陰で、政界の注目は石破茂前政権を支え、「影の総理」とまで称された重要人物、森山裕氏の動向に集まっています。森山氏が連立政権の安定と国会運営にいかに不可欠な存在であるか、その舞台裏を探ります。
 高市早苗新首相、自民党と日本維新の会による連立政権樹立後
高市早苗新首相、自民党と日本維新の会による連立政権樹立後
「影の総理」森山裕氏の存在感と総裁選での動き
森山裕氏は、第2次安倍政権から岸田政権にかけて歴代最長の1534日間、国会対策委員長を務め上げました。与野党を問わず幅広い人脈を持つことで知られ、石破政権下では党務から国会対策までを一手に引き受ける「影の総理」と評されていました。先の自民党総裁選では、森山氏自身は明確な支持を表明しなかったものの、地元・鹿児島県連の党員票が高市氏を約1000票上回ったことから、小泉進次郎防衛相を支持したと見られています。その卓越した調整能力と政治手腕は、新政権にとっても無視できない存在感を示しています。
高市新体制の人事と麻生氏の影響力
高市新首相は、幹事長に鈴木俊一前総務会長、総務会長に有村治子元女性活躍相と、いずれも麻生派に属する二名を起用しました。これは「露骨な論功行賞人事」との批判も出ており、政界では麻生太郎元首相が1年ぶりに副総裁に返り咲いたことで、再び実権を掌握したとの見方が強まっています。しかし、この人事の背景には、新政権が抱える潜在的な課題も浮き彫りになっています。特に、連立から離脱した公明党との関係構築がその一つです。
公明党との溝:麻生氏と森山氏の対照的な役割
現在、連立から離れた公明党の斉藤鉄夫代表は、物価高対策を盛り込んだ2025年度補正予算案への賛成に含みを持たせているものの、今後、野党側に傾倒する可能性も指摘されています。もしそうなれば、高市政権の国会運営は困難を極め、次期選挙においても自民党にとって大きな脅威となり得ます。この状況下で問題となるのが、麻生元首相と公明党の長年の確執です。麻生氏が公明党幹部を「がん」と呼んだことがあるなど、両者の関係修復は極めて困難とされています。
このような背景から、高市政権には公明党との新たなパイプ役が不可欠です。昨年5月、当時の岸田文雄首相がパーティー券購入者の公開基準を公明党や維新が主張する5万円超に引き下げた際、これに強く反対する麻生氏を森山氏が押し切った経緯があります。この出来事を通じて、森山氏は公明党との信頼関係を深めたとされており、公明党との対話において森山氏が果たす役割は計り知れないものがあります。
維新との連立維持:森山氏の「お目付け役」としての期待
自民党幹部は、森山氏が日本維新の会とも良好な関係を築いている点を指摘しています。大阪の副首都構想や衆院議員定数1割削減といった政策課題は、一筋縄ではいかない難題です。もしこれらの調整がこじれ、維新が政権から離脱するような事態になれば、衆議院で内閣不信任決議案が可決される可能性も否定できません。
こうしたリスクを回避するため、自民党幹部からは「首相は森山氏を閣僚として取り込み、維新に対する『お目付け役』に据えておくべきだった」との声が上がっています。森山氏の広範な人脈と交渉能力は、連立政権の安定、特に維新との円滑な関係維持にとって極めて重要な要素です。高市政権の未来は、森山氏のようなベテラン政治家の手腕に大きく左右されることになりそうです。
高市早苗新政権は、新たな政治の時代を切り開く上で、内部の結束と外部との関係構築という二重の課題に直面しています。森山裕氏のような経験豊富な人物の活用は、これらの課題を乗り越え、政権の安定と政策推進を確かなものにするための鍵となるでしょう。